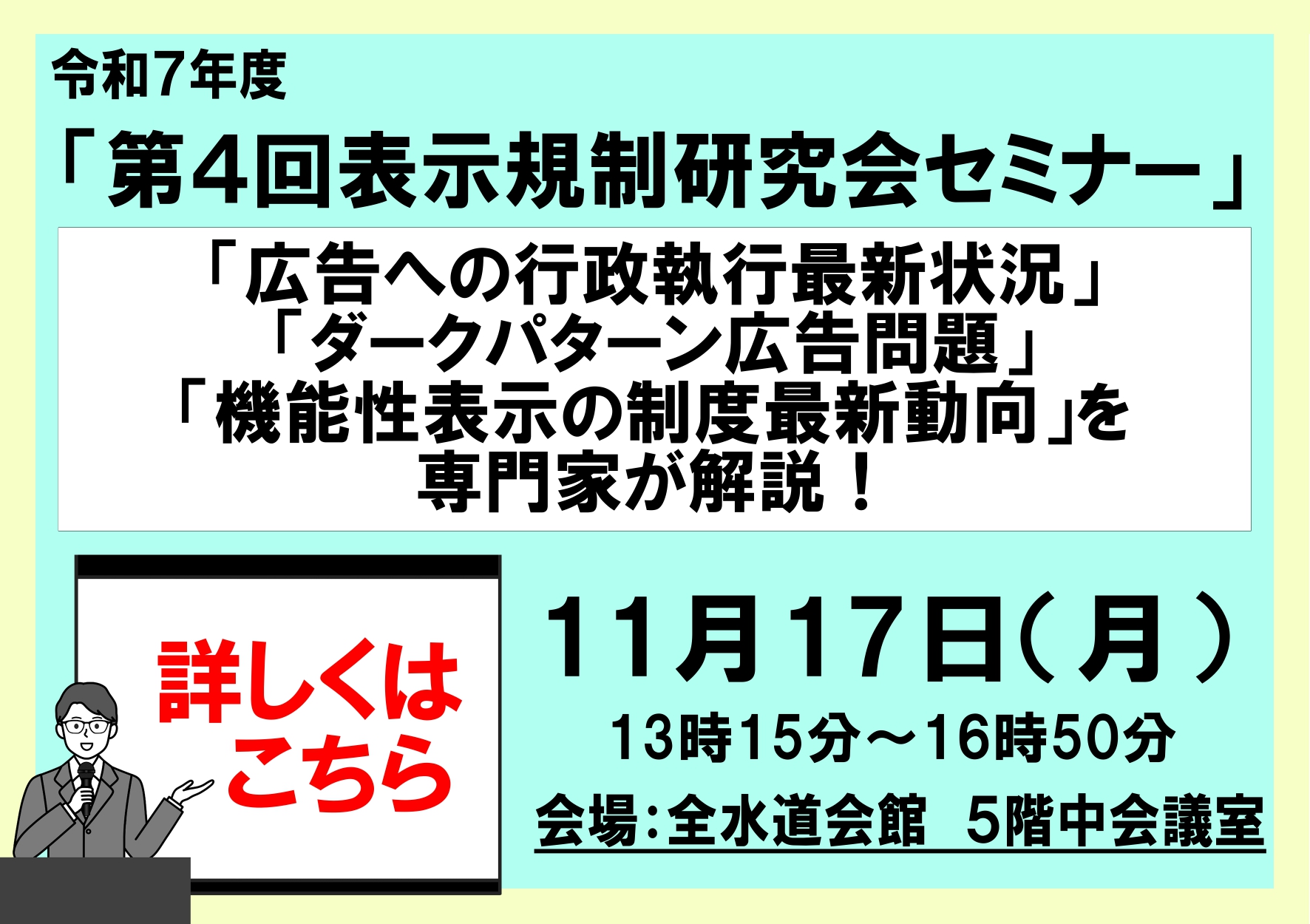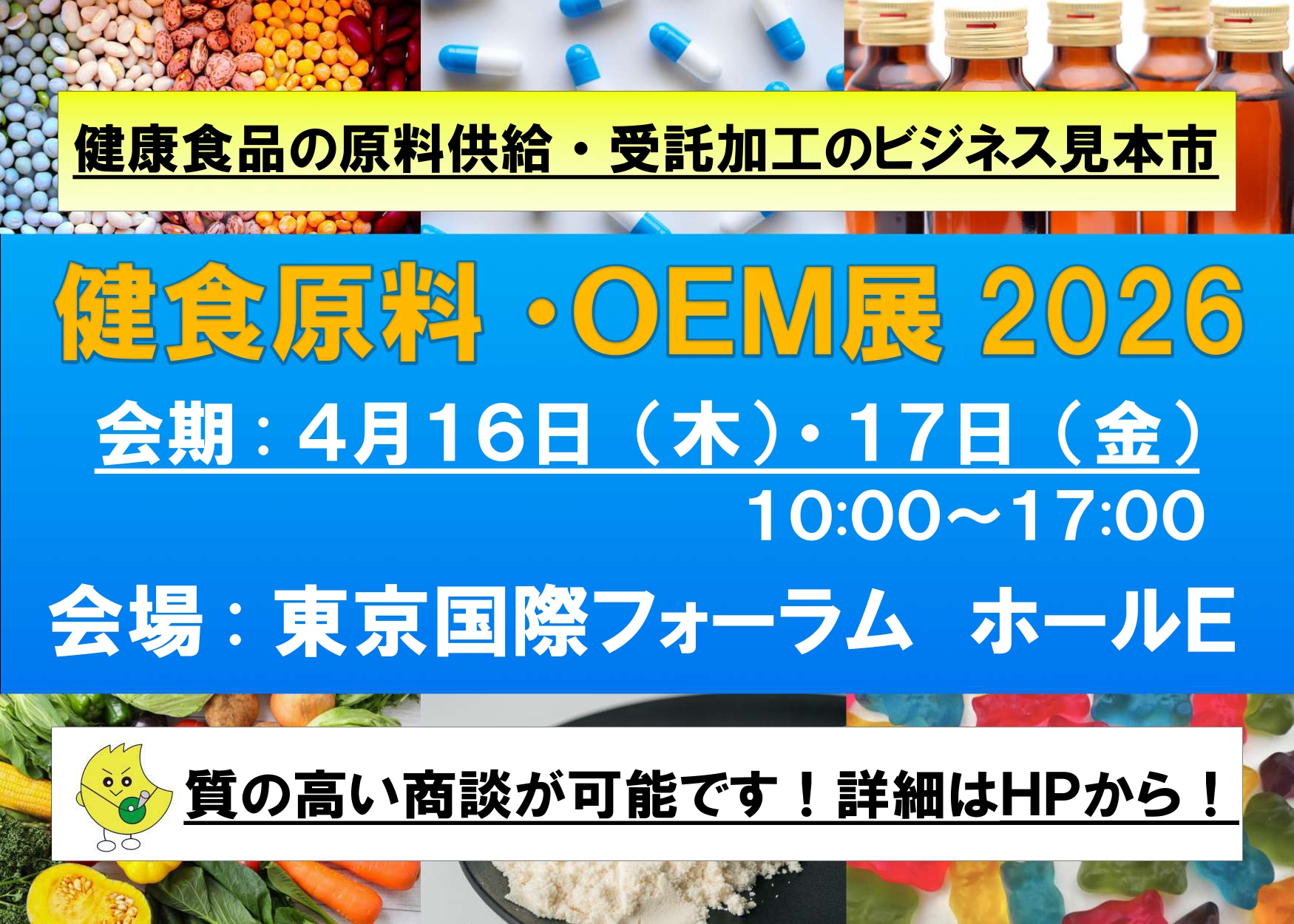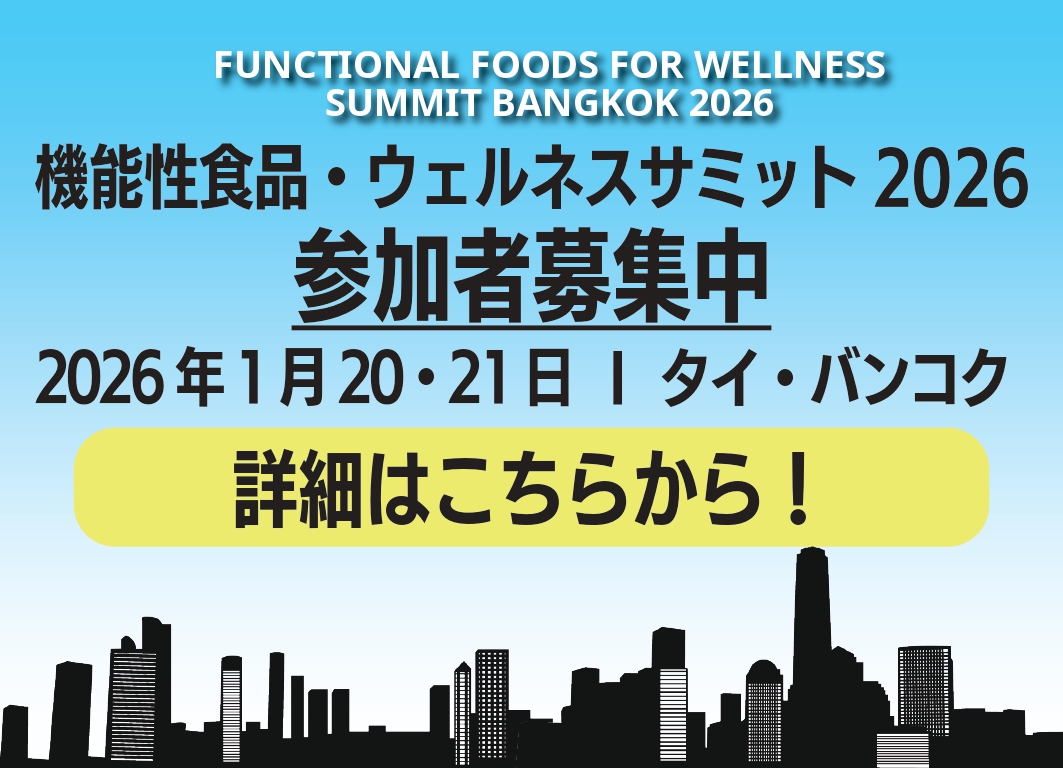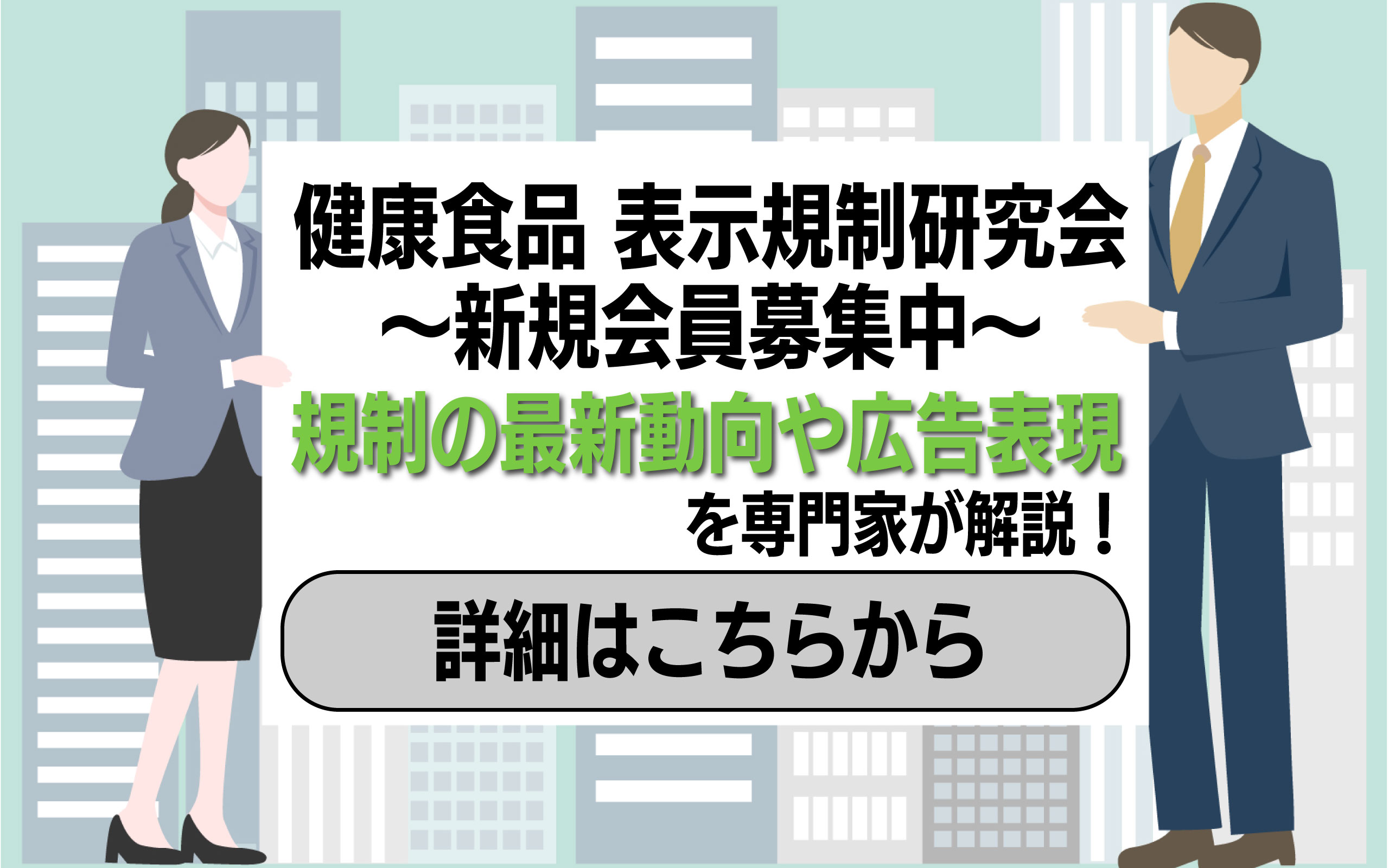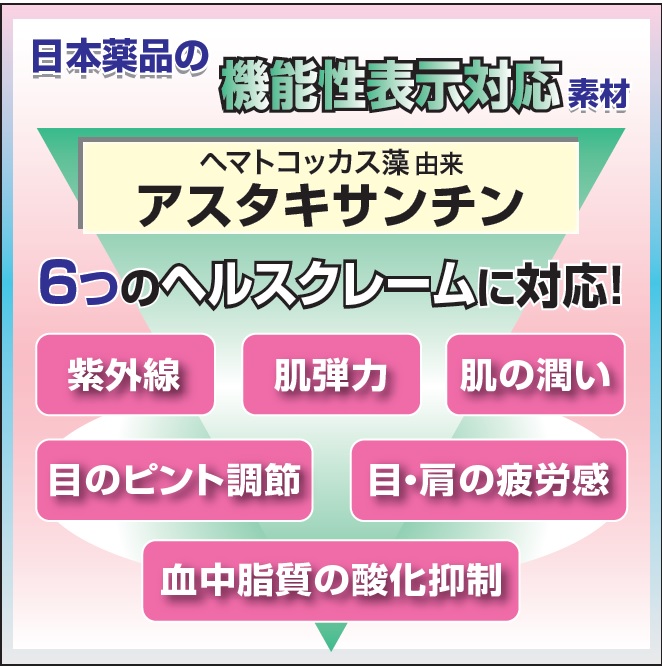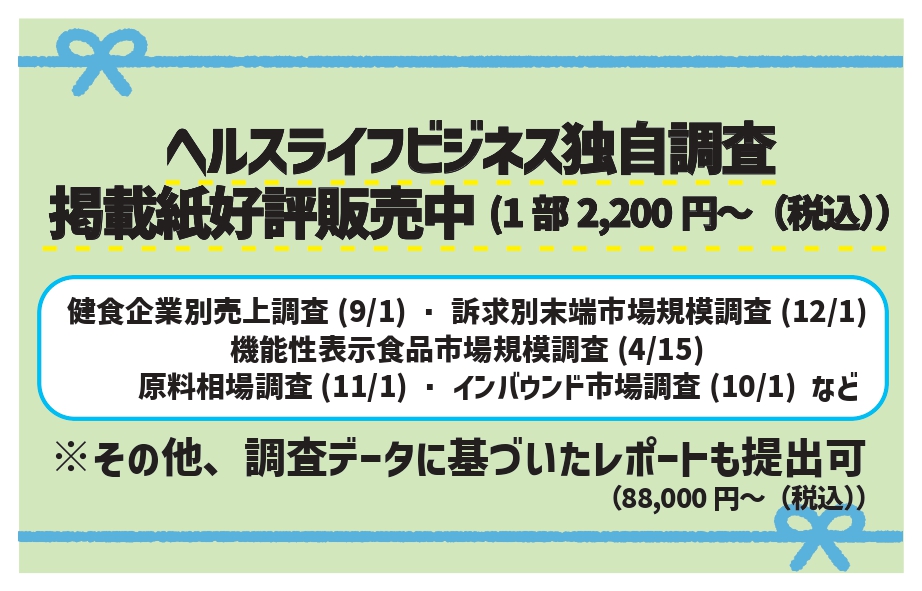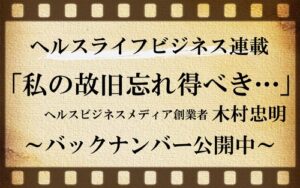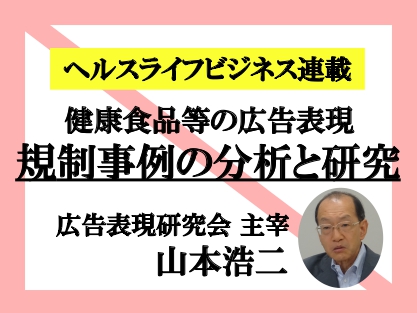厚生省に取り締まってもわないと…。(139)
バックナンバーはこちら
当時は、テレビのニュースや新聞記事で健康食品に関する役所の発表を見かけると、慌てて官庁まで取材に行く。そうしないと役所の資料は手に入らなかった。しかも各省庁にある記者クラブ優先である。所属していないマスコミはそこで発表した後でないと、役所の法改正や政策発表などの資料をもうことはできなかった。
文句を言うと、「記者クラブに入ればいいじゃない」と何度か言われた。業界紙も含めて記者クラブに入っていないマスコミはごまんとあった。ところが零細新聞などはまず入れない仕組みになっていた。すでに所属している新聞社の推薦がいる。さらには記者を1人その記者クラブに張り付けなければならない。つまりお金もかかるのだ。零細企業にそんなゆとりはない。
こうして役所が大手マスコミを優遇していた。それで大手マスコミは大本営発表をそのまま書く。役所発表の記事を見ると、よく同じような内容の記事が各社の紙面を飾ることになる。
それでも零細マスコミも手を子招いていたわけではない。その発表のことを知っていればその役所の部署の廊下に詰めて、記者クラブの発表が終わるのを待つという手もあった。
ところが経企庁が健康食品の調査をやっていることを知る由もなかった。さらに関係している省庁ならまだしも、馴染みのない経企庁では教えてくれる人もなかった。それで今回はマスコミが騒いで始めて知ったというわけだ。
この頃、カバンの中にはノートとカメラ、それに都内の地図を必ず入れていた。地下鉄千代田線の霞が関の駅で降りて地上に出ると農林省の脇に出た。地図を広げて経企庁の場所を探した。しかし今思い起こしても、経企庁がどの辺りにあったかはっきりした記憶がない。なんだか文部省の近くにあったようにも思う。とにかく何とかたどり着いて、電話で聞いていた部署に行った。外の廊下の壁に机の配置図と名前が示されている。一番廊下に近い机に座っている人が担当のようだ。“ノンキャリ”には違いない。近づいて名刺を出すと机に平積みにした資料を1部くれた。
「ちょっと話を聞きたいんですが」というと、「なんでしょう」と折り畳みの椅子を出してくれた。聞くことは一つしかない。なぜ経企庁が健康食品の調査をしたのかということだ。我々の想像だと厚生省が背後にいるはずだが、そういっても「はいそうです」とは言わないだろう。
それで「なぜ健康食品を取り上げたんですか」と理由を聞いた。すると「たまたまですよ」と軽くいう。そうたまたまでしょうねェ、とこちらも思う。なんたって厚生省に頼まれただけだから…。「健康食品はだいぶ薬事法や景表法に違反する販売をやっているんですね」というと、やや得意げに、「ここまでだとは思いませんでしたよ」という。そこで「違反はどうするんですか」と聞いてみた。すると「それは厚生省に取り締まってもらわないと」と言い出した。
これで十分だった。役所が自分に必要のない調査をするわけがない。役所が動くときはたいがい産業育成か取り締まりが相場だった。ところが担当者からは育成に関する言葉は聞かれなかった。つまり取り締まることが目的だと思えば間違いない。取り締まりが必要な官庁が首謀者ということである。
帰り際に農林省に行った。この頃の農林省の地下には地方の物産などを販売している場所があった。ちょっとした市場のようだが、その奥に食堂があった。そこでマグロ丼が安く食べられた。
この頃の霞が関の中央官庁はどこものんびりしていた。たいがいの官庁の出入りは自由で、警備員にチェックされることもなった。セキリティなどという言葉を聞いたこともなかった時代だから日本中の役所がそうだったのかもしれない。
ついでに農林省の食品流通局へ行った。食品油脂課というのが加工食品を管轄している部署で、そこに西野さんという人がいた。取材で知り合ったのだが、農林省の役人は気さくで良い人が多かった。西野さんはもちろんノンキャリで、気軽な立場だったせいか、なんでも話が出来た。実は後年現在の会社を立ち上げたとき、新聞の名称「ヘルスライフビジネス」の名付け親にもなってくれた人でもある。
廊下からガラス越しに中を覗くと椅子に座っていた。ドアを開けて顔を出すと、向こうから気が付いて、「大変だったね」と経企庁のことを知っていた。
(ヘルスライフビジネス2020年1月15日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)