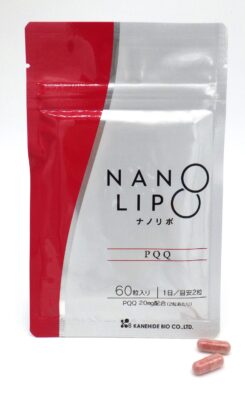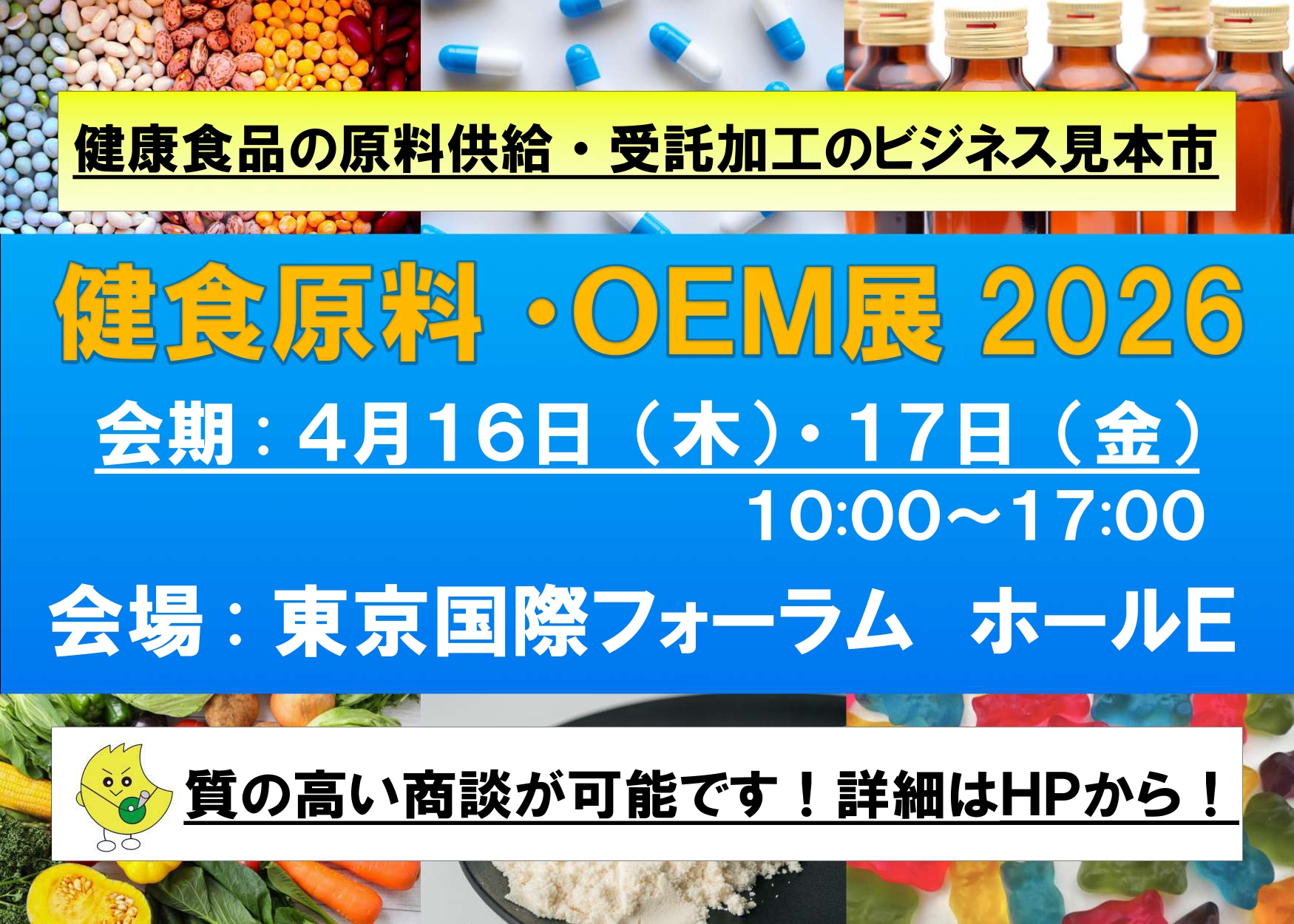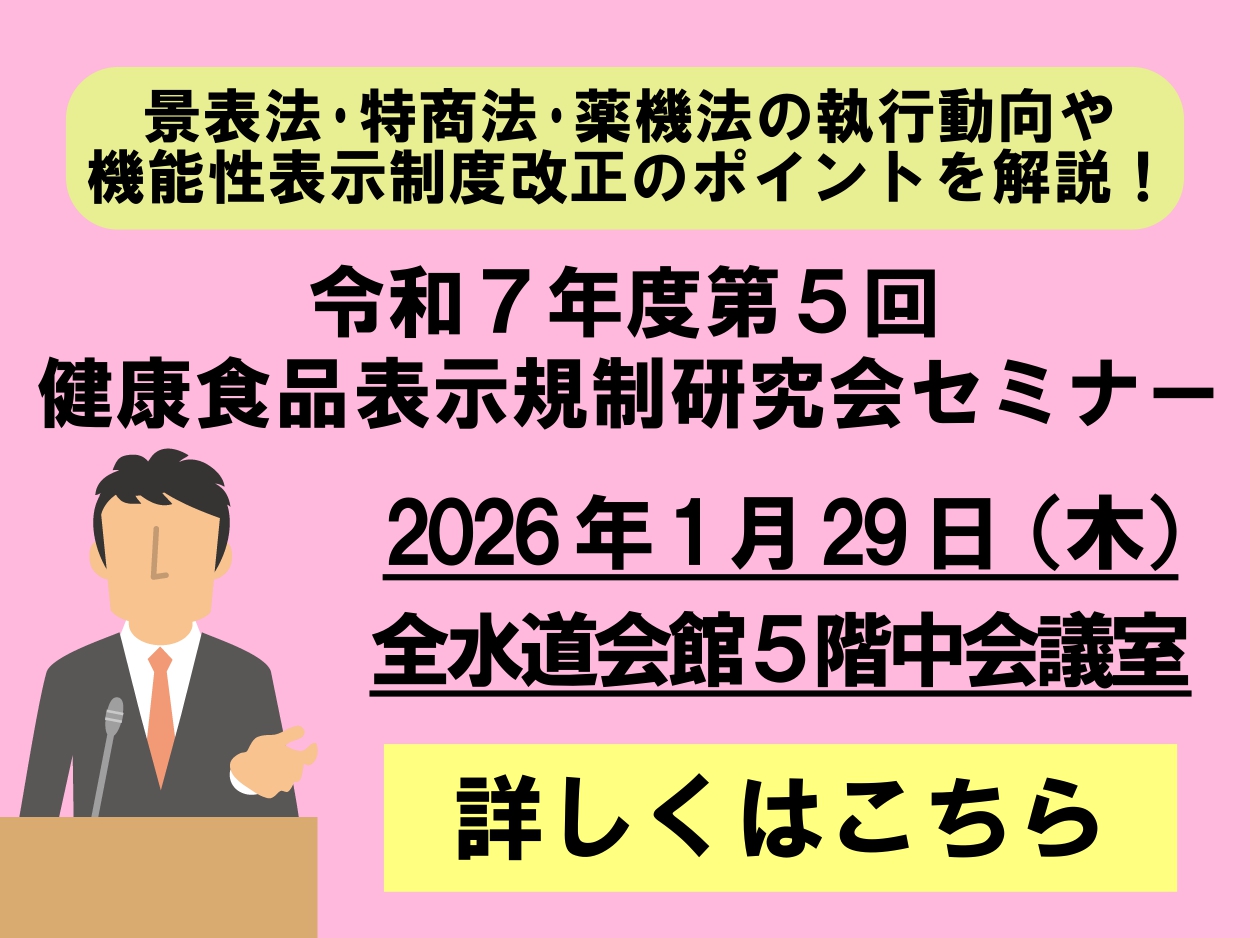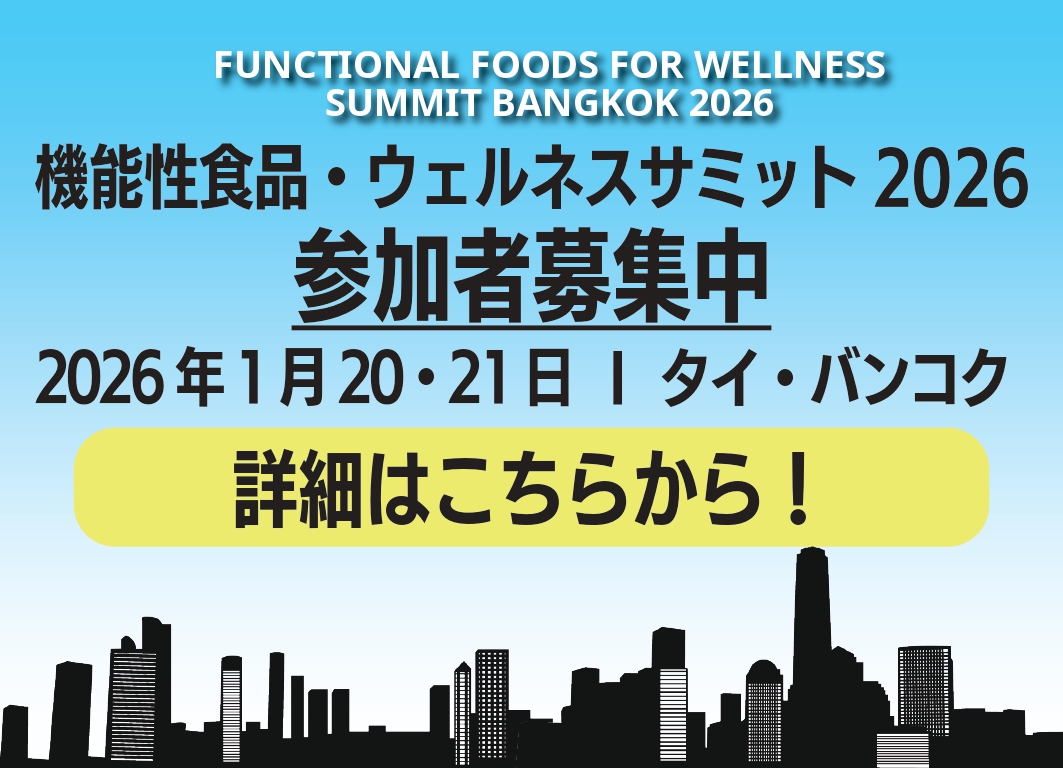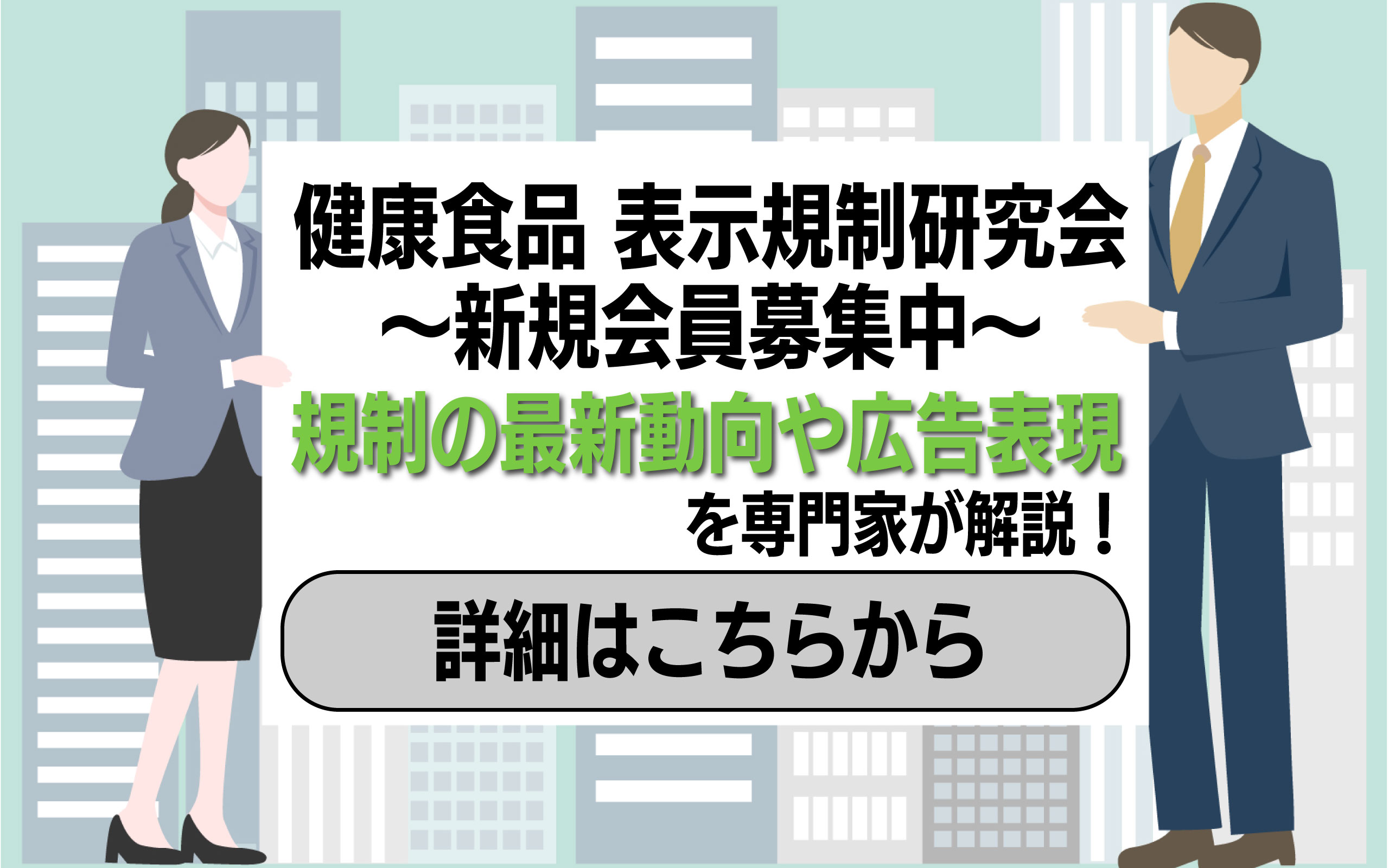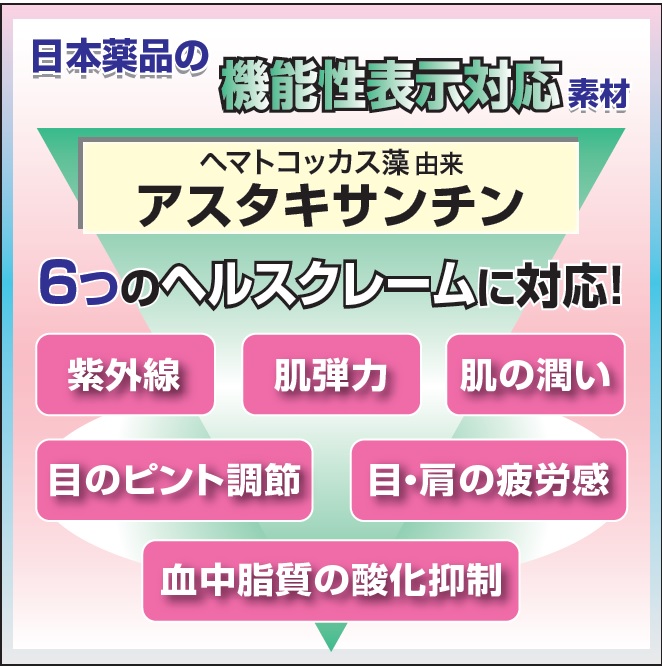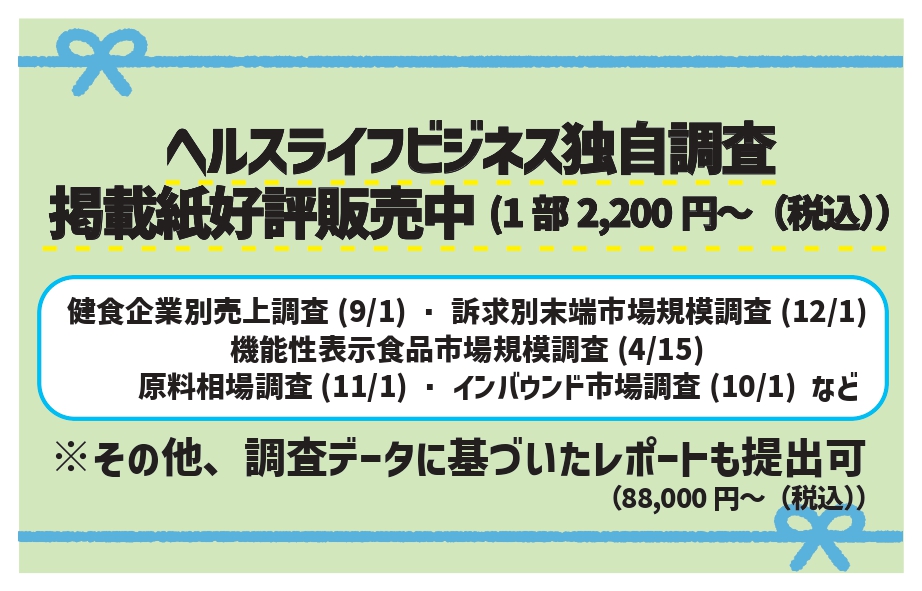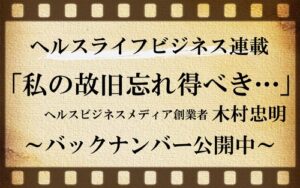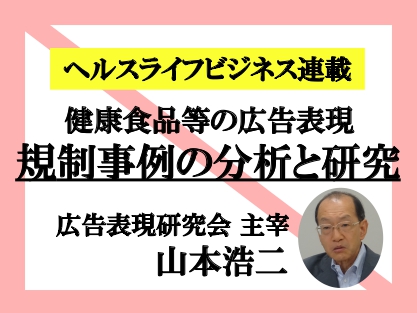- トップ
- ビジネス , ヘルスライフビジネス
- 自然治癒力を生かす新しい栄養…
自然治癒力を生かす新しい栄養学を提唱(149)
バックナンバーはこちら
福場さんの講演が終わると、渡辺先生が壇上に上がった。開口一番「医薬は病気の時に治療の〝脇役〟を果たすだけである」との一言はインパクトがあった。場内の人たちは何の話が始まるのかと、耳をそばだてた。その頃の誰もが病気治療の主役は医療と薬だと思っていた。しかし渡辺先生は真逆のことを言い出した。ところが話が進むうちに、なるほどと思うようになる。少なくとも私はそうだった。
というのも病気を治すのは生身の身体に備わった自然治癒力であるという。この自然治癒力というと、免疫力と捉えがちだが、渡辺先生の言う自然治癒力はもう少し広い。身体のバランスを正常に保つ生体恒常性の維持、細菌やウイルス、自分の変質した細胞を処理するなどの生体防御、さらに古くなったり傷ついたりした細胞を修復・新生する自己再生などの能力を合わせたものを言う。
そしてそれを支えているのは栄養だというのだ。だから病気を治す主役は栄養であるべきだというのが、渡辺先生の主張であり、アデル・デービスの主張でもある。
人は病気になるとそのストレスで体内の栄養素を著しく消耗する。このため、消耗される栄養素を強化しないと自然治癒力が低下し、早期の回復は出来ない。デービスはこれにいち早く気付いた。
そして、それまでの研究報告を下地に1960年代に病気ごとに作り上げたのがこの「栄養プログラム」の本だという。
このなかで注目したのがセリエ博士の「ストレス学説」だった。1930年代にカナダの精神医学者のハンス・セリエが提唱したが、このストレス学説の中で栄養との関係を明らかにしていることを知っている人は意外に少ない。ストレスがかかると、それに対抗するために特定な栄養素が失われ、それが補給されなければ組織の破壊が起き、しまいには死に至る。
セリエはネズミにビタミンCやマグネシウムでこのことを明らかにしている。このため病気を回復させるためには栄養の整った食事、すなわち「完全栄養」を与えることが必要だ。そのためには微量栄養素や繊維分が失われている精製加工食品をやめ、全粒小麦などの未精製の食品を使った食事を提供すること、さらにストレスで大量に失われるビタミンCやパントテン酸などの栄養素はサプリメントで補給することを勧めている。
「この栄養療法には2つの特徴がある」と言う。
一つはビタミンなどの大量投与をすることで全身の代謝を正常化し、即効的な効果を得る。そして時間をかけてストレスで壊れた組織を修復する。
もう一つは病気になるプロセスは健康から半健康を経て病気になって行く。このプロセスに従って栄養の強化をすることで、病気なる前に健康な状態に復帰する。つまり予防が可能になる。
人は遺伝的な違いにより、生まれながらの差がある。さらに置かれた環境でストレスの加わる量も違う。このため各人で体内の栄養の要求量に違いが出てくる。前者がテキサス大学のウイリアム教授の生化学的個体差という学説であり、後者はセリアが実証したストレス学説である。
渡辺先生は「確かに細菌やウイルスの感染症は抗生物質やワクチンの開発で克服でき、医学は目覚ましい進歩を遂げた」と矛先を医療に向けた。
1798年にイギリス人医学者エドワード・ジェンナーが天然痘のワクチンの種痘を世に出し、以降コレラ、ペストからインフルエンザに至るまで、さまざまなワクチンが感染症や伝染病の予防に成果を上げている。
また、1928年にアレクサンダー・フレミングによって発見された抗生物質ペニシリンが第二次世界大戦の兵士を感染症から救い、1944年にワックスマンらによってストレプトマイシンが発見され、死の病と言われた結核が克服された。
「しかし、この目覚ましい医学の進歩が仇となった」と言う。なぜか。それは第二次大戦後、病気の質が一変したからだ。
(ヘルスライフビジネス2020年6月15日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)