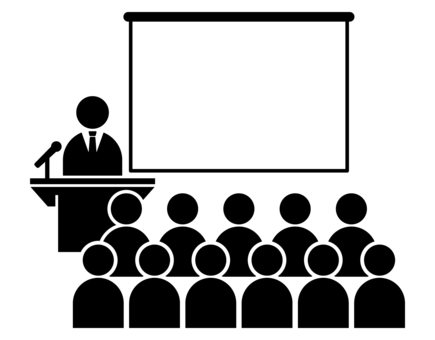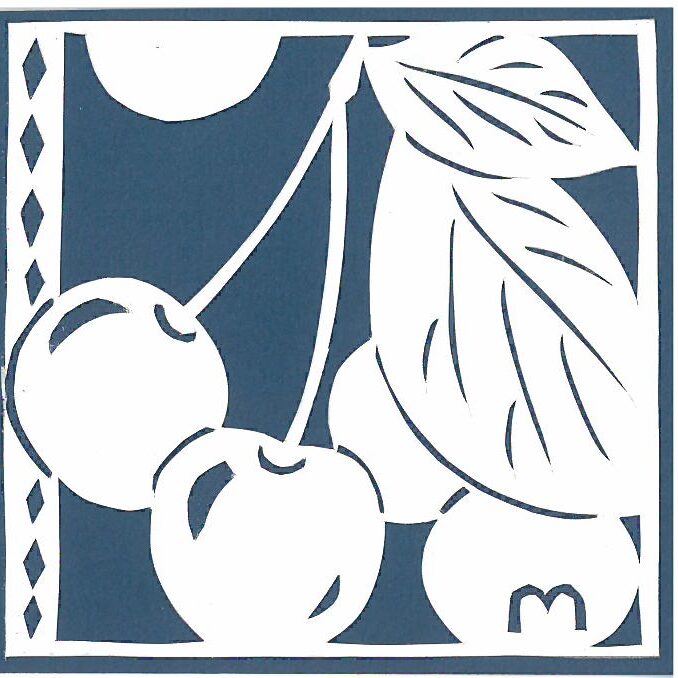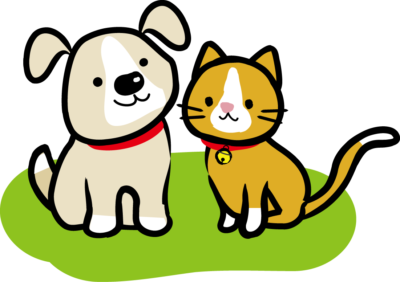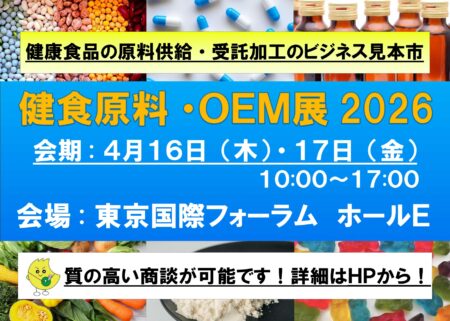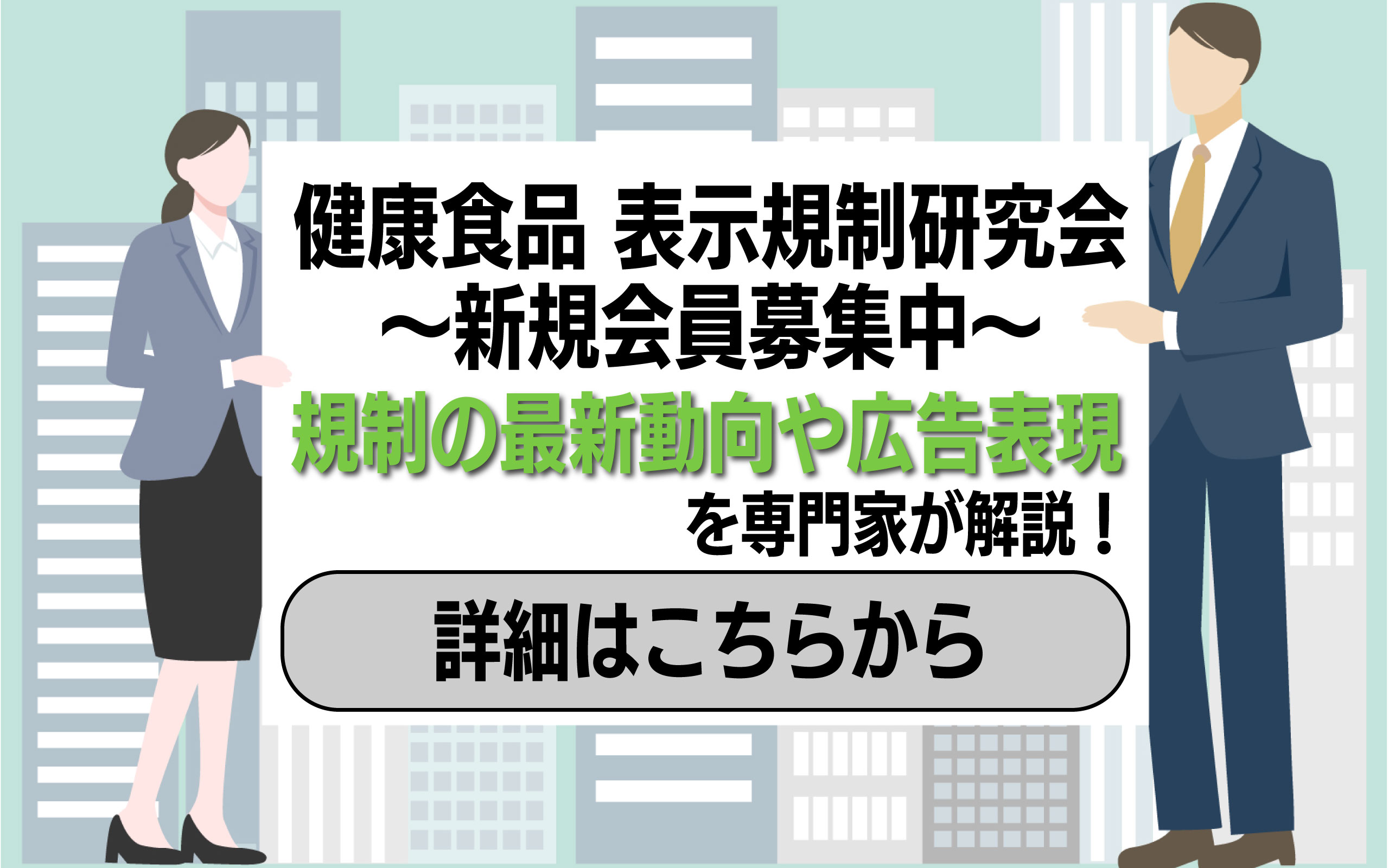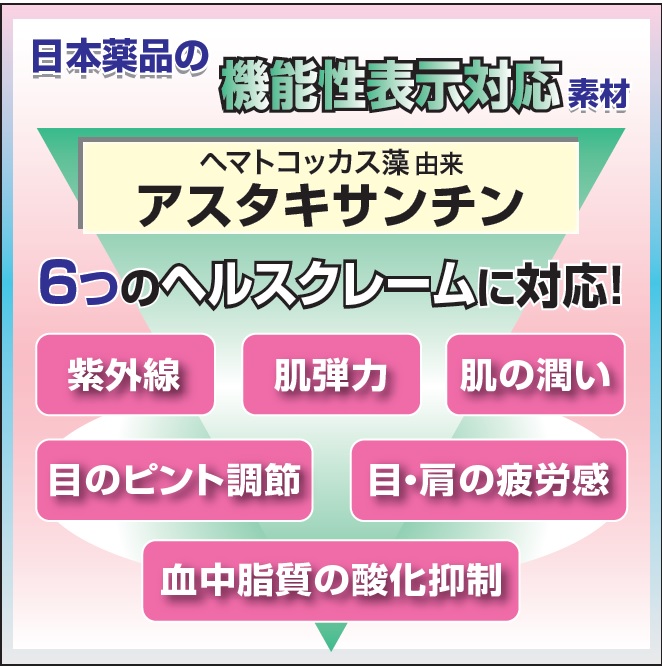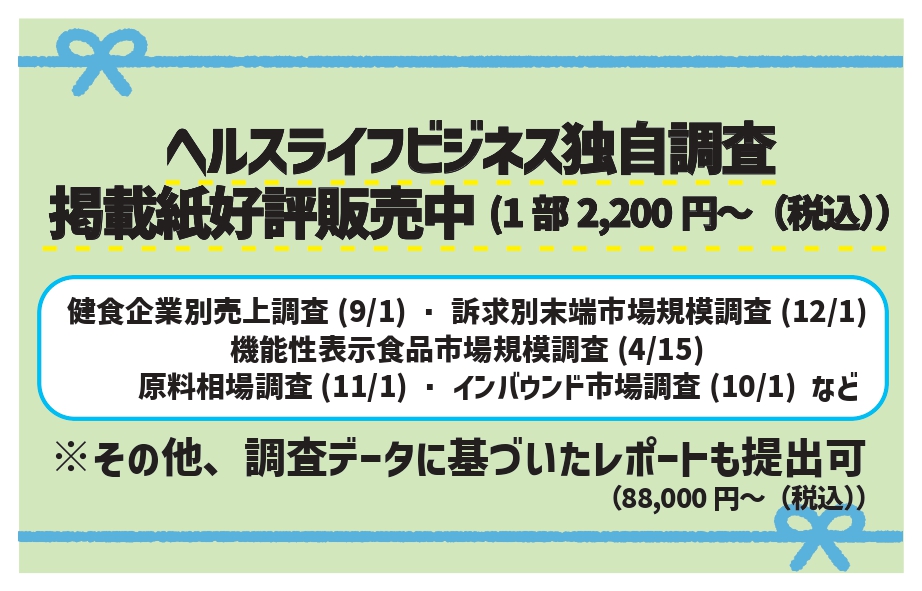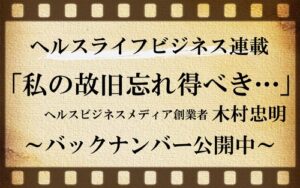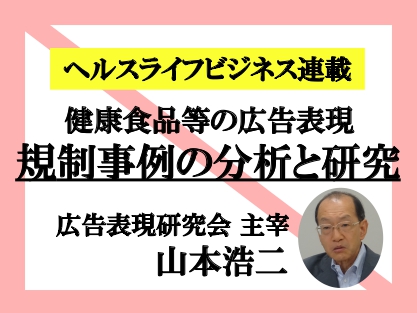厚生省、公取が相次いで取り締まりへ(152)
バックナンバーはこちら
経企庁の健康食品の調査発表から2月近く経った。ほとぼりが冷めたと思っていたら、5月21日になって今度は厚生省が取り締まりの通知を出した。
昼下がりに編集部で雑談である。お茶をすすりながら、葛西博士に聞いた。「なにか関係があるのかんなあ」と。クッキーかじりながら役所の通知の文書を見ていた葛西博士が「うん、そう書いてある」と言う。
通知は厚生省監視指導課が全国の都道府県の衛生担当者に出している。タイトルは「無承認無許可医薬品の指導取り締まりの徹底について」とある。
なぜ徹底しなければならないかというと、経企庁の調査であるからだ。これには効能効果があるような印象を与えた健康食品が多いと指摘されていた。
「出来レースでしょう」と言うと、そうだと思うが、文面で見る限りは経企庁から「調べたら薬事法違反が野放しだ」と言われたに等しいという。他の行政機関から業者に甘く見られていると指摘されたとしたら、普通ならば厚生省はカチンとくるはずだ。
「とにかくこれが厳しい取り締まりに十分な根拠を与えたことは間違いない」と博士は分析する。指摘されたのは商品の売り場に一緒に置たり、新聞の・雑誌の広告を見て商品の説明を請求した人に送ってくる使用経験の感謝文、体験談集のことだ。広告やパンフレットに効能効果を謳えば薬事法違反に違いないが、業者も手が込で来て、感謝状や体験談の中でそれとなく効果匂わす。
「しかし匂わせたつもりでも、役所が臭いと思えばなかなか逃れられない」と葛西博士。効能効果の暗示に当たれば違反だと46通知に書かれている。ちゃんとした違反なのだ。しかしそうしたことが横行していることを経企庁の調査はあぶり出した。
だから「監視指導のなお一層の徹底を図られるとともに、違反を発見した場合には、事案に応じた告発、行政処分を行うなど厳正に措置されたい」と通知では力が入る。
監視指導とは見つけて指導しろということで、いわゆる行政指導だ。行政の定義では行政指導は助言、指導、勧告だ。つまり「違反に当たるから止めなさい」という程度で処分は伴わない。止めればそれで許される。ところが、それでも言うことを聞かないと行政処分になる。つまり薬事法違反として警察に回される。とにかくこれで行政指導や取り締まりを徹底せよと全国の担当部署に号令した。
「ちょっと、やばいですね」と岩澤君は言う。確かにやばいが、それにしても本当に取り締まりが出来るのだろうか。例えばどうやってそんな文章を手に入れるんだろうか。
「御取り捜査みたいなことをやるんですかねェ」と岩澤君が言うと、「そんなこと出来るわけがないだろう」と葛西博士は自信ありげだ。監視指導課は厚生省薬務局の中にあった。都道府県で取り締まりの最前線は各地域の保健所だ。保健所には薬剤師は基本的にいないらしい。人件費がかかるからだ。それで彼らがいるのは都道府県の役所だ。しかも保健所は夏の時期は忙しい。食中毒などの衛生面の仕事があるからだ。人を増やして取り締まるには今以上の予算も必要だ。だからと言って、今年度の予算を増やした形跡はない。
「徹底的な取り締まりなど出来るわけがないさ」と博士。さすがに詳しい。「じゃあなんで…」と吉村君。新人記者らしい疑問だ。「Good Qestion」とカッコをつける。葛西博士の悪い癖だ。
「脅しだよ。脅し」
マスコミが取り上げて、業者が震え上がれば目的はほぼ達成したのも同じだ。あとは、業者のタレコミを待つ。いつもの手だという。
ところが今回は行政の方もやや手が込んでいた。公正取引委員会が5月24日に効能効果違反を景品表示法でも取り締まるという通知を都道府県宛てに出したことを30日に公表した。わずか9日の内に2回も取り締まりの通知がマスコミを賑わした。
「ホップ、ステップ、ジャンプですね」と岩澤君。「馬鹿だねェ。喜ぶようなことじゃないよ」と葛西博士。“ブームの健康食品、公取も取り締まりへ”との新聞の見出し。さしもの業界もこれには凹んだ。
(ヘルスライフビジネス2020年8月1日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)