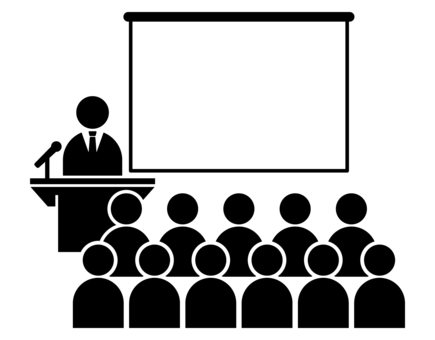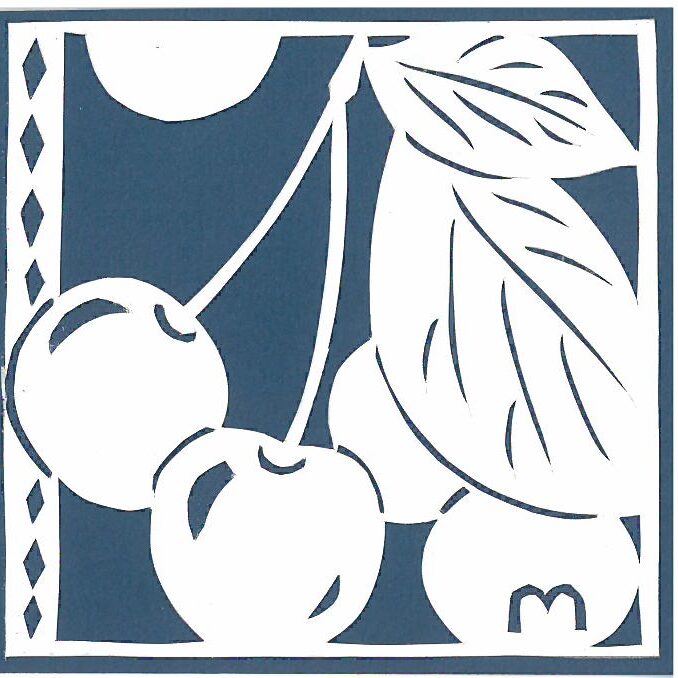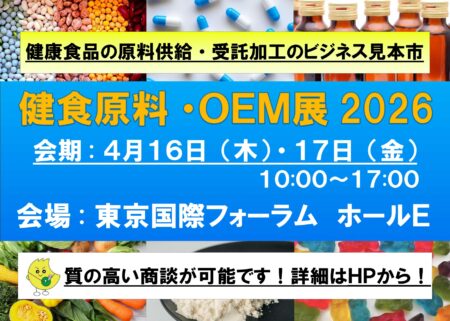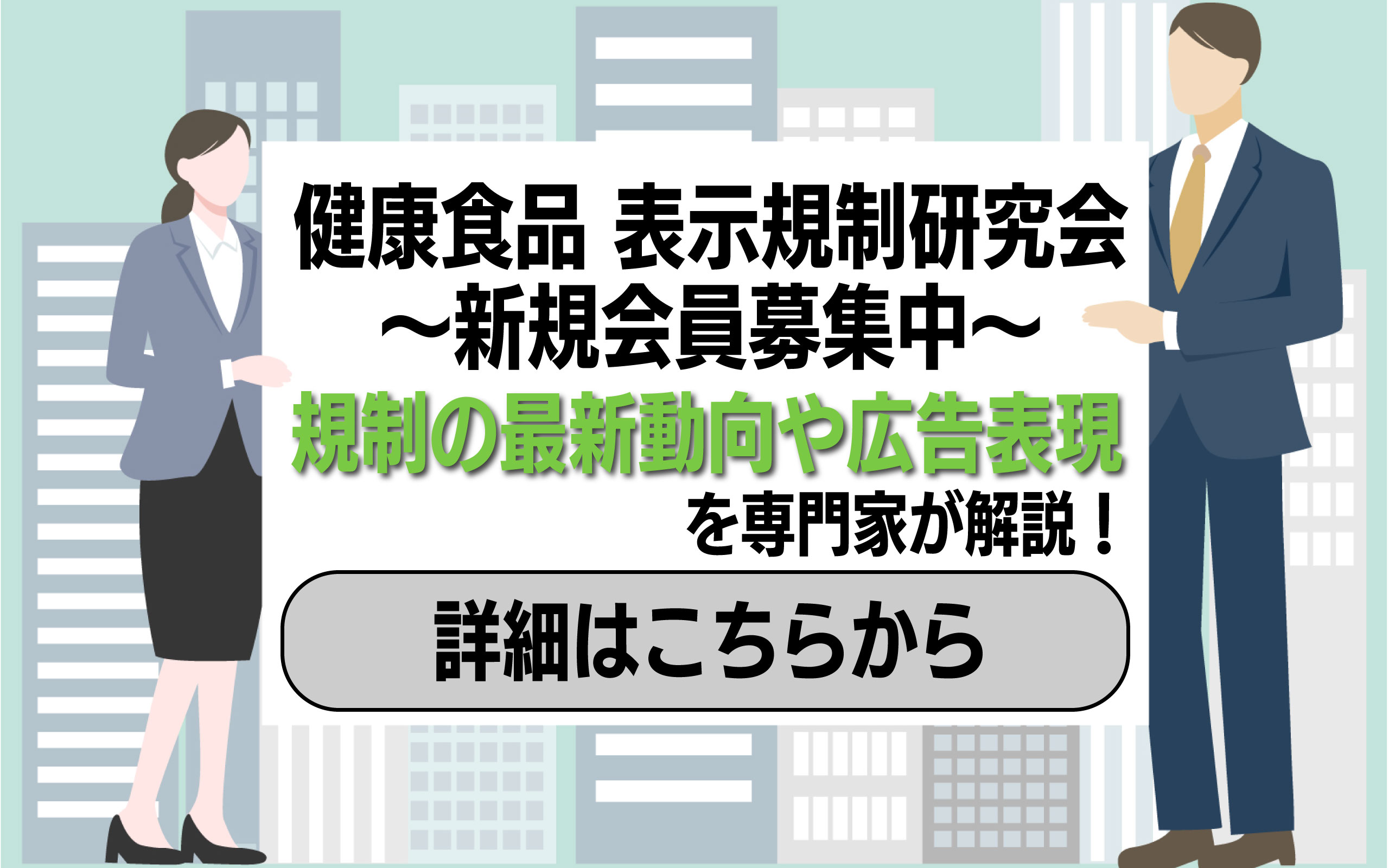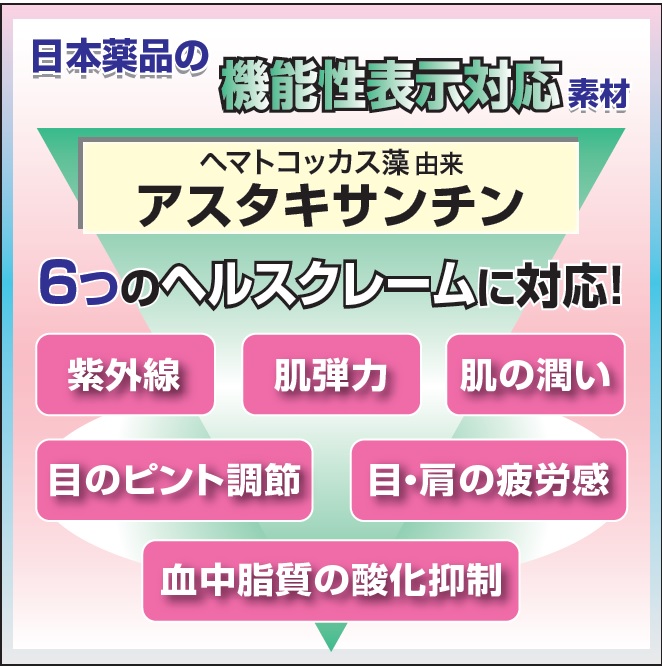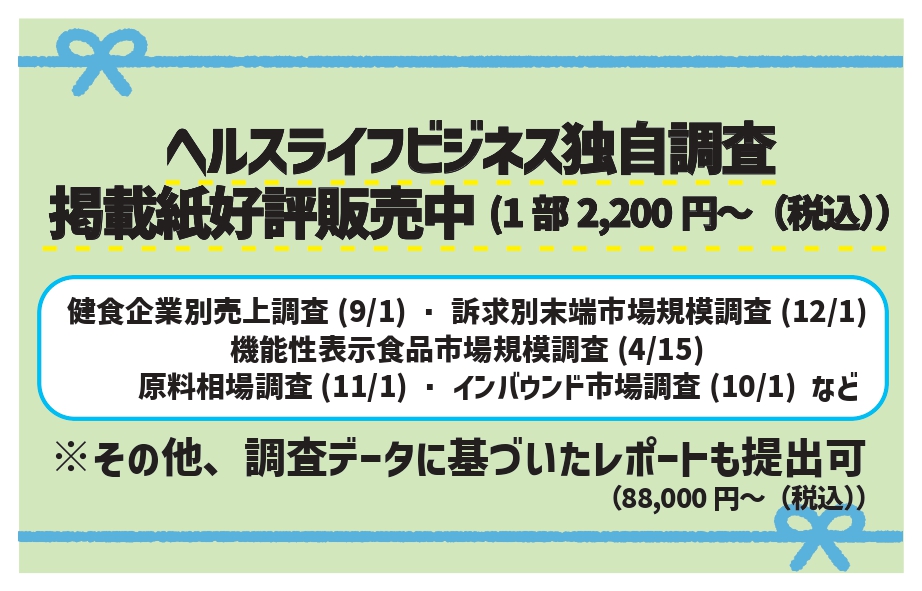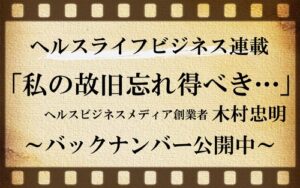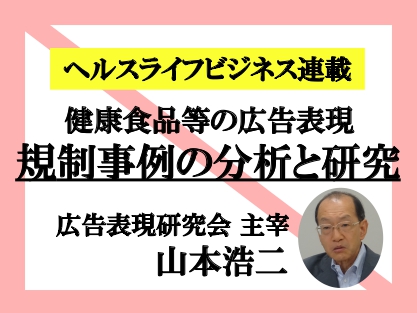- トップ
- ビジネス , ヘルスライフビジネス
- 研究予算は涙銭で大先生はお金…
研究予算は涙銭で大先生はお金集めに奔走(158)
バックナンバーはこちら
今度は私が葛西博士を突っついた。ヨダレを拭きながら、顔をもたげた博士が私の方を向いて、「ナニ」。まだねぼけている。
「所要量にビタミンEが入るんだよ」というと、さすがに目が覚めたのか、「それはすごい」と福場さんの話を聞き始めた。
話を聞いていた人の驚きには理由があった。1970年代から80年代にかけてのビタミンブームは米国で起こった。そこで注目されたのがマルチビタミンでありビタミンCで、ビタミンEは3番手だった。ところが、このブームが80年代初頭日本に上陸すると、マルチビタミンは消えてなくなり、主役はビタミンEとビタミンCになっていた。
日本の錠剤・カプセル型のビタミンのブームはビタミンCから始まった。1977年(昭和36年)にタケダの「ハイシー」が発売された。そしてしばらくするとビタミンCブームになった。証券会社に勤め始めたばかりの叔母が家に遊びに来て、ビタミンCが万能薬のような話をしていたのを覚えている。東京オリンピックが始まる2年ほど前の事だったと思う。母は看護師をしていたが、病院からもらってきた医療用のビタミンCが家に沢山あったのを覚えている。それで何かあるとすぐにビタミンCを飲んだ記憶がある。
一方、1938年(昭和13年)にエーザイがビタミンE製剤「ユベラ」を出した。戦前の話だ。天然型ビタミンE剤「ユベラックス」を発売したのは1977年(昭和55年)の事だった。だから80年代に日本でサプリメントのビタミンブームが起きた時には、すでにビタミンCもEも知っている人は多かった。しかしこれらは市販薬であってサプリメントではなかった。
この頃、世界ではビタミンを食品とする国が多かった。もちろん医薬品とする国も少なからずあった。その一つが日本である。なぜ栄養成分なのに医薬品になったかというと、ビタミンB1がその始まりだと言われる。“江戸病”と言われた脚気を治す物質・オリザニンを米の胚芽の中から、東京大学農学部の鈴木梅太郎が発見した。後のビタミンB1だが、脚気の治療に効果があるということでこれが医薬品になった。これでビタミンは医薬品に数えられることになった。後に三共(第一三共)が医薬品を出している。
これ以降、日本ではビタミン類は医薬品になった。医薬品だから薬事法で規制されていた。この規制では医薬品でないものだけが食品とされていた。加えて、錠剤やカプセルなど医薬品に似たサプリメントは薬事法の規制の対象になっていた。
薬事法の運用マニュアルである46通知では、形状と成分、効能効果、用法用量の4つの基準を総合的に判断して、これに触れないものだけが食品として販売が許されてきた。
しかし、食品と言っても生鮮食品は対象外だが、加工食品はこの規制の対象になっていた。だから栄養所要量の中にビタミンEが入るというのは、食品成分でもあることを国が認めたことで画期的なことだったのだ。
その晩の食事には大半の人が一緒になった。ステーキが有名なレストランだったが、ロブスターやカキなどのシーフードもあった。ワインやビールを飲みながら歓談を楽しんだが、その席の主役は福場さんだった。もちろん本人もご機嫌だった。
隣の席が空いたので、そこに座って何の気なしに聞いてみた。「最近はどんな研究をしているんですか」と。すると思いもしない答えが返ってきた。「だいぶ以前から研究なんてしてませんよ」と言う。意味が分からなかった。大学教授とは研究と生徒の教育が仕事だと思っていた。ところがそうではなく「お金集めですよ!」と言う。ニコニコしているが、あながち冗談ではなさそうだ。その頃、若造がった私には分からなかったが、今ならよくわかる。若い学者を育てるために研究資金を集めるのがそれなりの立場になった学者の仕事なのだ。
米国の国立衛生研究賞(NIH)は医学系の研究費を一手に握っている。その年間予算は今では年間4兆円を超える。ところが日本版NIHとして始まった国立研究開発法人日本医療研究開発機構は2020年で1268億円、関係のある国立研究開発法人農業・食品産業技術産業機構も644億円で、両方足しても2000億円にならない。国の年間予算は米国が485兆円ほどで、直接税と間接税をたして200兆円を超える日本の倍以上だが、研究予算の取り方が半端ではない。その分日本の研究予算はみじめなものだ。
「銭の無いことは首の無いことと同じ」とは近松門左衛門の「冥途の飛脚」の中のセリフがだが、世界で2番の経済大国に上り詰めた日本は見せかけだけに過ぎないことを思い知らされた。
(ヘルスライフビジネス2020年11月1日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)