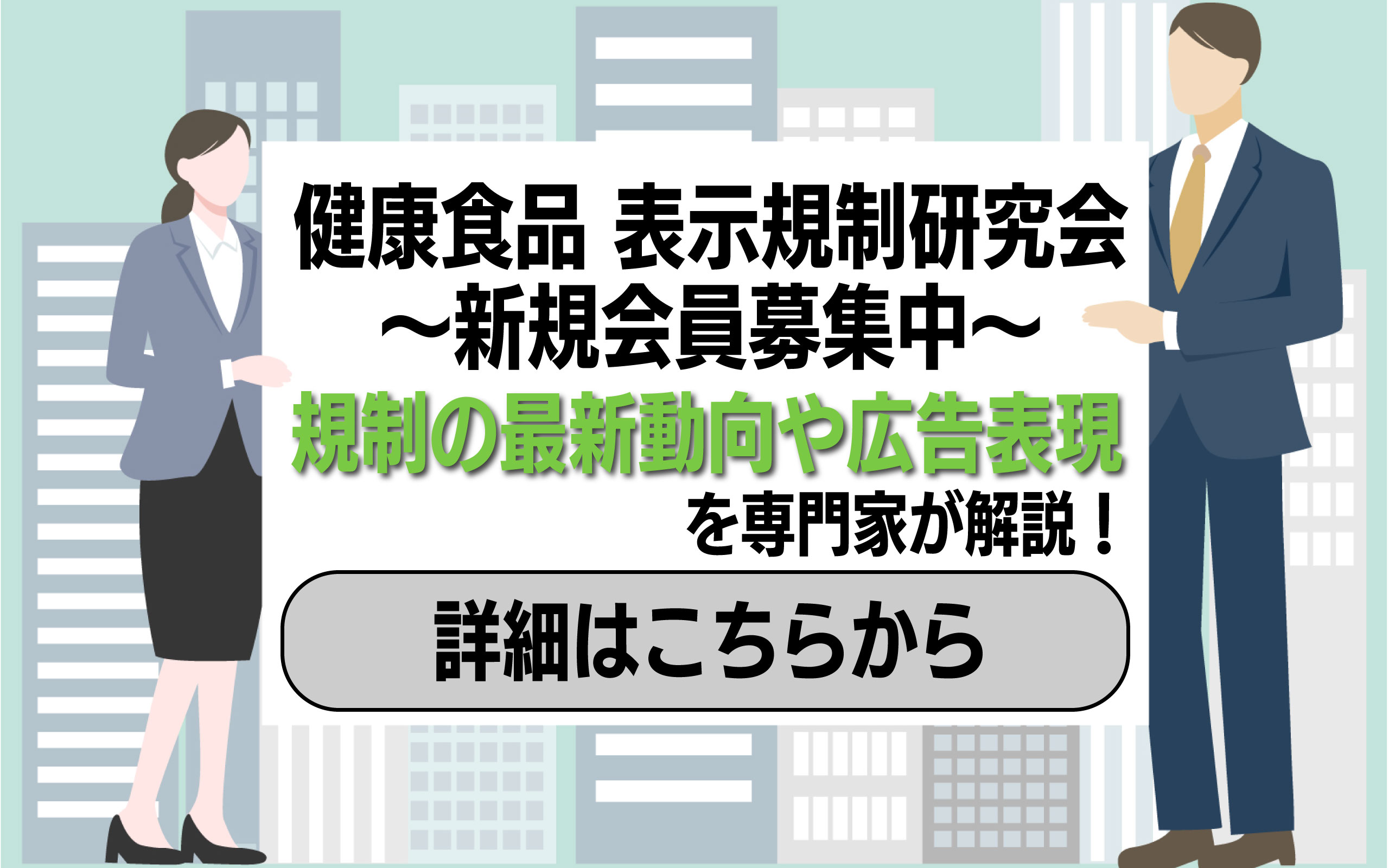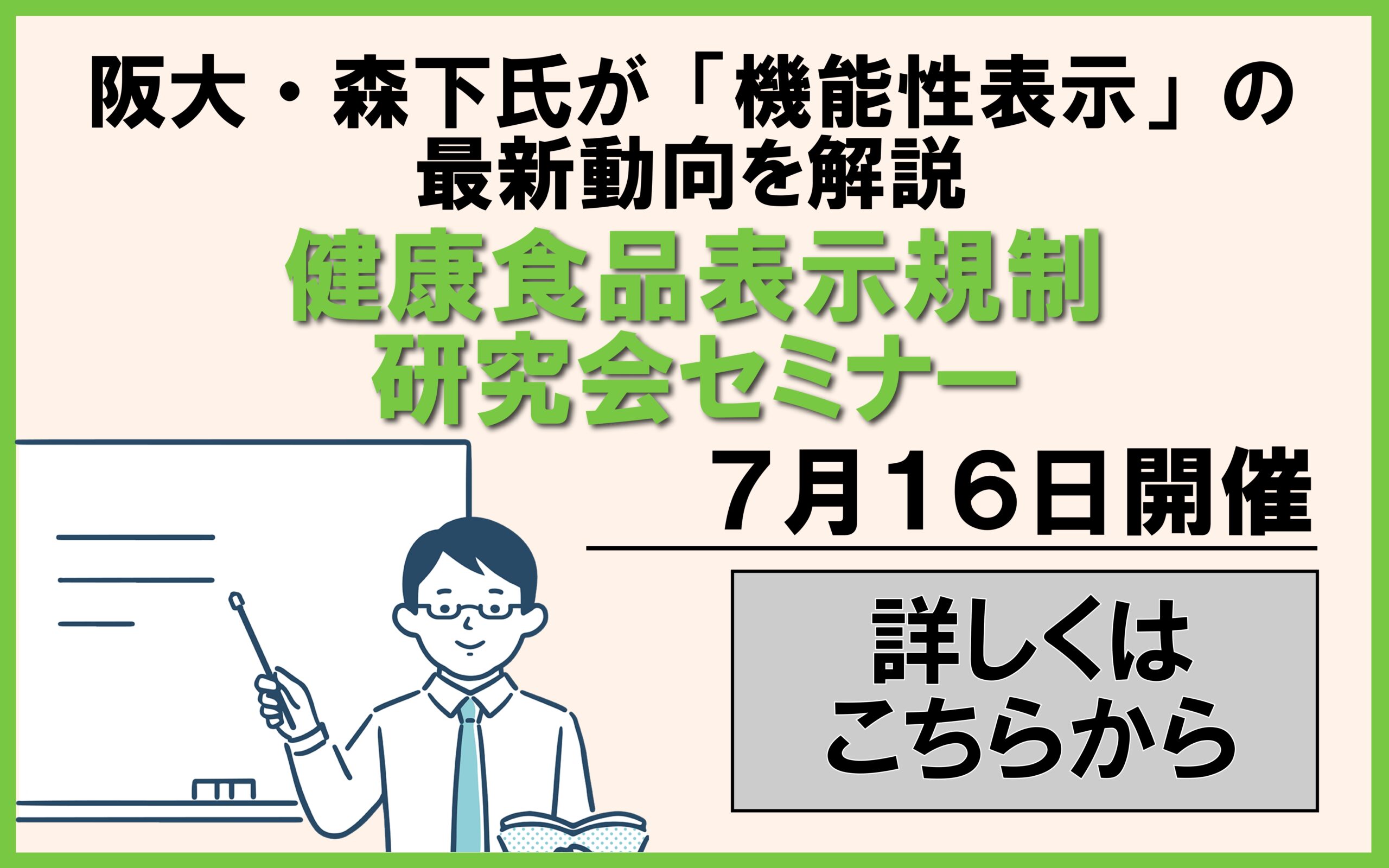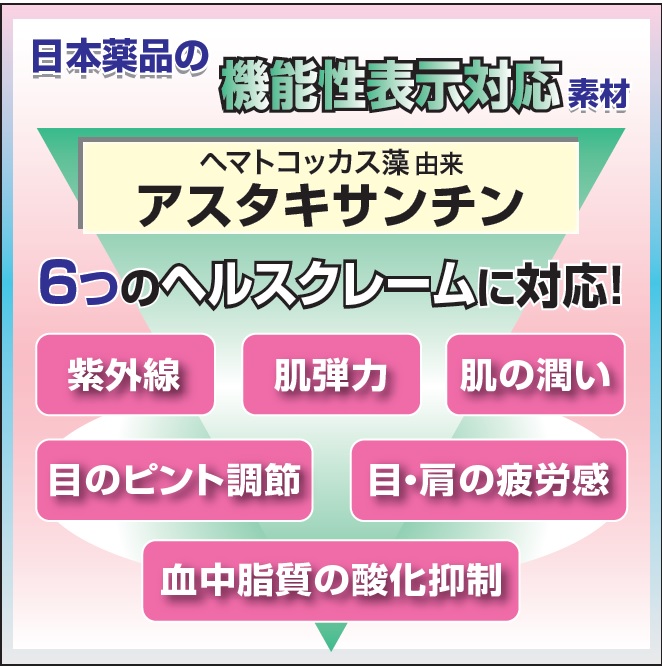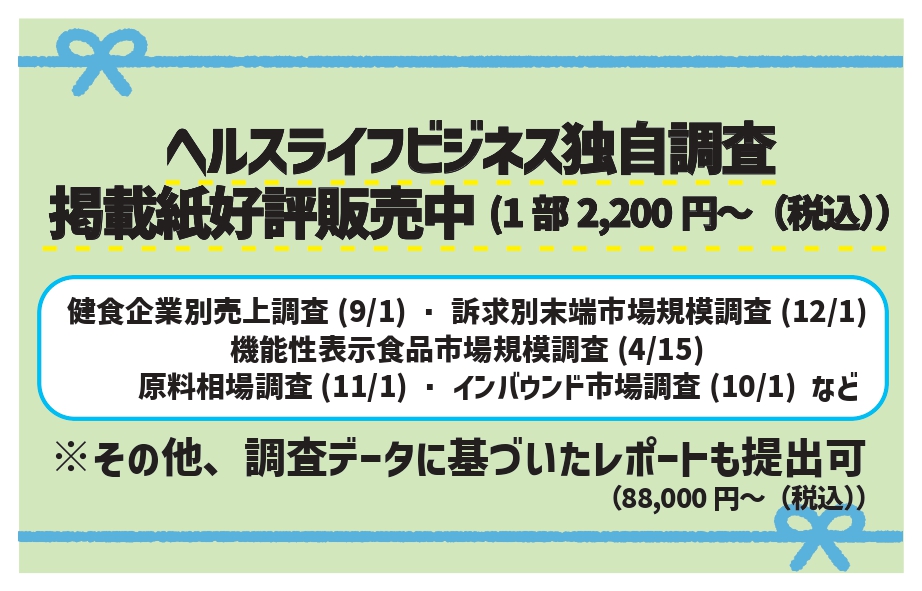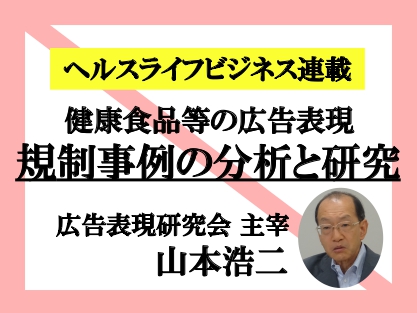【新連載】私の故旧忘れ得べき(第1回)
食品の技術系の出版社に就職した
「人は死ななかったらどうなるんだろう」
ふと友人が呟いた。30年以上前のことだ。この問いはいまだに私の心に残っている。人は生きてもせいぜい100歳程度だ。平均寿命なら男の私は80歳だから、順当に行けばゴールラインを踏むまで、まで後19年ある。衰え行く体を引きずりながら生きてゆくには結構しんどい長さでもある。さらにあと100年生きられるとしても、気が遠くなる。だから死なないことになったら、おそらく生きることの価値もなくなりそうだ。退廃した日常の繰り返しだけが続く、壁も檻もない監獄の中で暮らす囚人ようになるに違いない。人は死というゴールがあるから走り続けることができる。そして生きてきた過去はゴールがあるから価値を生むのだ。
学生の頃、高見順という小説家の本を読んだことがある。昭和初期の文壇のことを書いた「故旧忘れ得べき」だった。このタイトルはスコットランド民謡のから拝借したもので、ロバート・バーンズの詩で知っている人もあるかも知れない。日本では「蛍の光」として知られている別れの歌だが、本来は過ぎ去りし日々や友を懐かしむ歌詞になっているらしい。私もこの仕事に付いて以来の過ぎ去った日々や人々を思ってみたくなる年代になった。そこでタイトルはこれを拝借して「私の故旧忘れ得べき」にすることにした。書くことは結構あるので、長い連載になる。「古きを訪ねて新しきを知る」という言葉があるが、役に立つかどうかは読者に任せ、私は書きたいことを書かせて頂く。しばらくの間お付き合い頂ければと思う。
1979年は暖かな冬だった。1月18日(木曜日)に、私は東京・湯島の食品研究社に初めて出勤した。お茶の水の東京医科歯科大学の近くで、本郷通りと蔵前通りの間の道をお茶の水方向から清水坂下に下って行く途中の左側のモルタルの建物の2階に事務所があった。当時、この出版社では食品の技術系の月刊誌2誌と単行本を出していた。
道路からドアを開け、階段を上ると、床は木造でギシギシ軋んだ。出社を告げると、丸顔でやたらに目がギョロついた太った中年男性が出てきた。社長の園田昭司氏である。社内には数人が居合わせたが、私の方をそれとなく関心ありげに見ている。
そちらの方をギロリと見やると、「新入社員の木村君です」と紹介した。仕事の話になると約束とは違っていた。雑誌の編集をすると思っていたが、「木村君には新聞の編集をしてもらいたい」という。新聞を出していることは知らなかった。断る理由もないので了解したが、編集部はここではないという。お茶の水の聖橋を渡った向こう側の駿河台らしい。園山社長に付いて本郷通りを行くと、中央大学の正門と反対側の路地を入ったモルタル2階建ての建物に入って行く。名前だけは山崎ビルといっぱしに付いていた。一室のドアを開けると、机に向かっていた2人の男がこちらを振り向いた。
「今度来てくれた木村君です」
6畳ほどの事務所の真ん中に石油ストーブ、床には深部やらパンフレットやらゴミが散乱している。3つの机が壁や窓に向かっておかれている。つまり私を入れて3人がこの新聞社のすべてだということがこのとき判明した。「騙された」と思ったが後の祭りだ。親や友人にも就職したことを告げていた。蓄えも底を突いている。給料が入るまで我慢して、早々に逃げ出そうと決めた。
(ヘルスライフビジネス主幹・木村忠明)
※第2回は9月20日(火)更新予定。