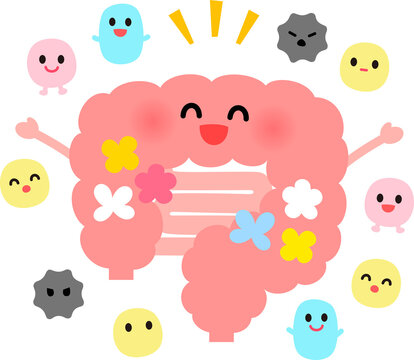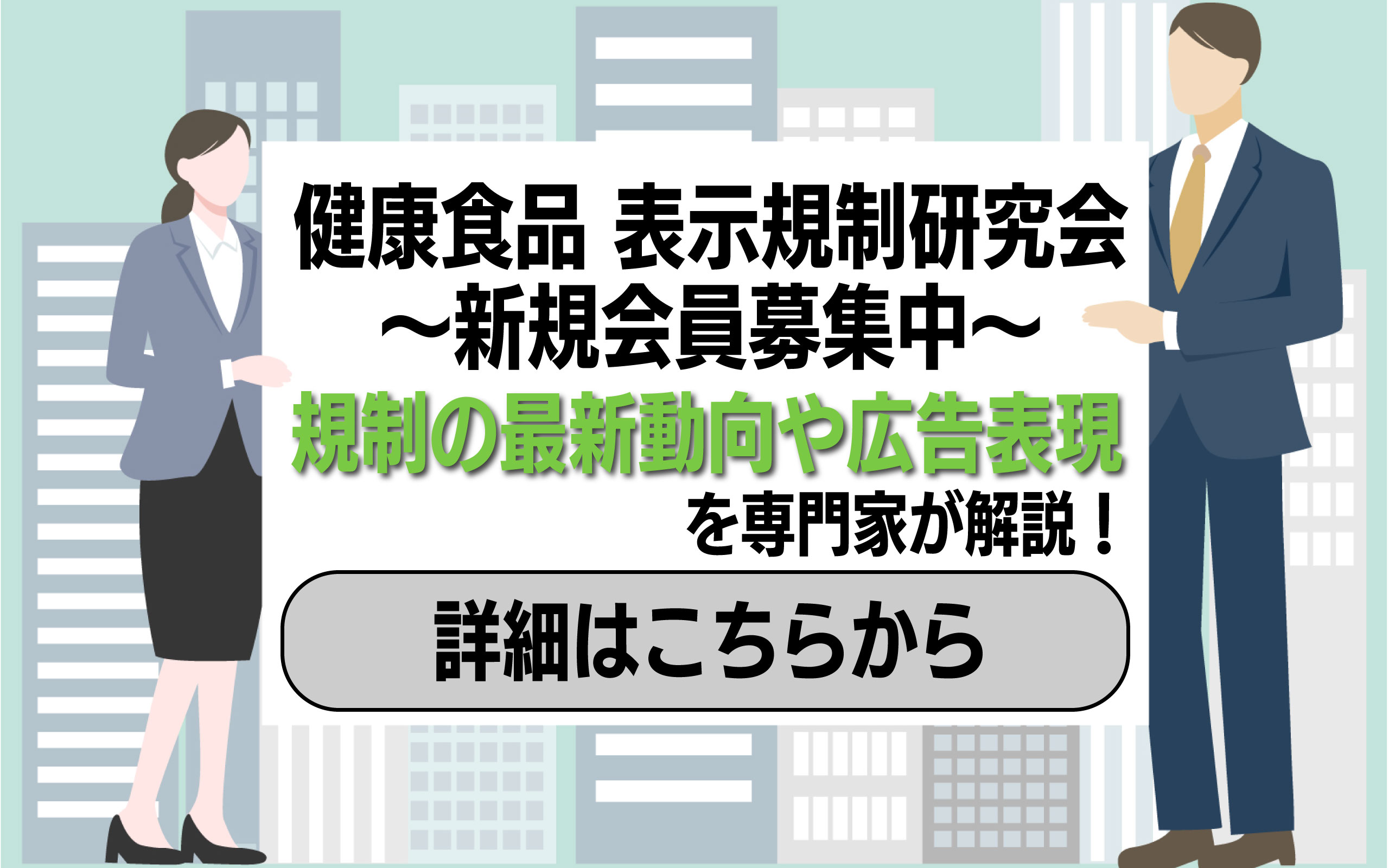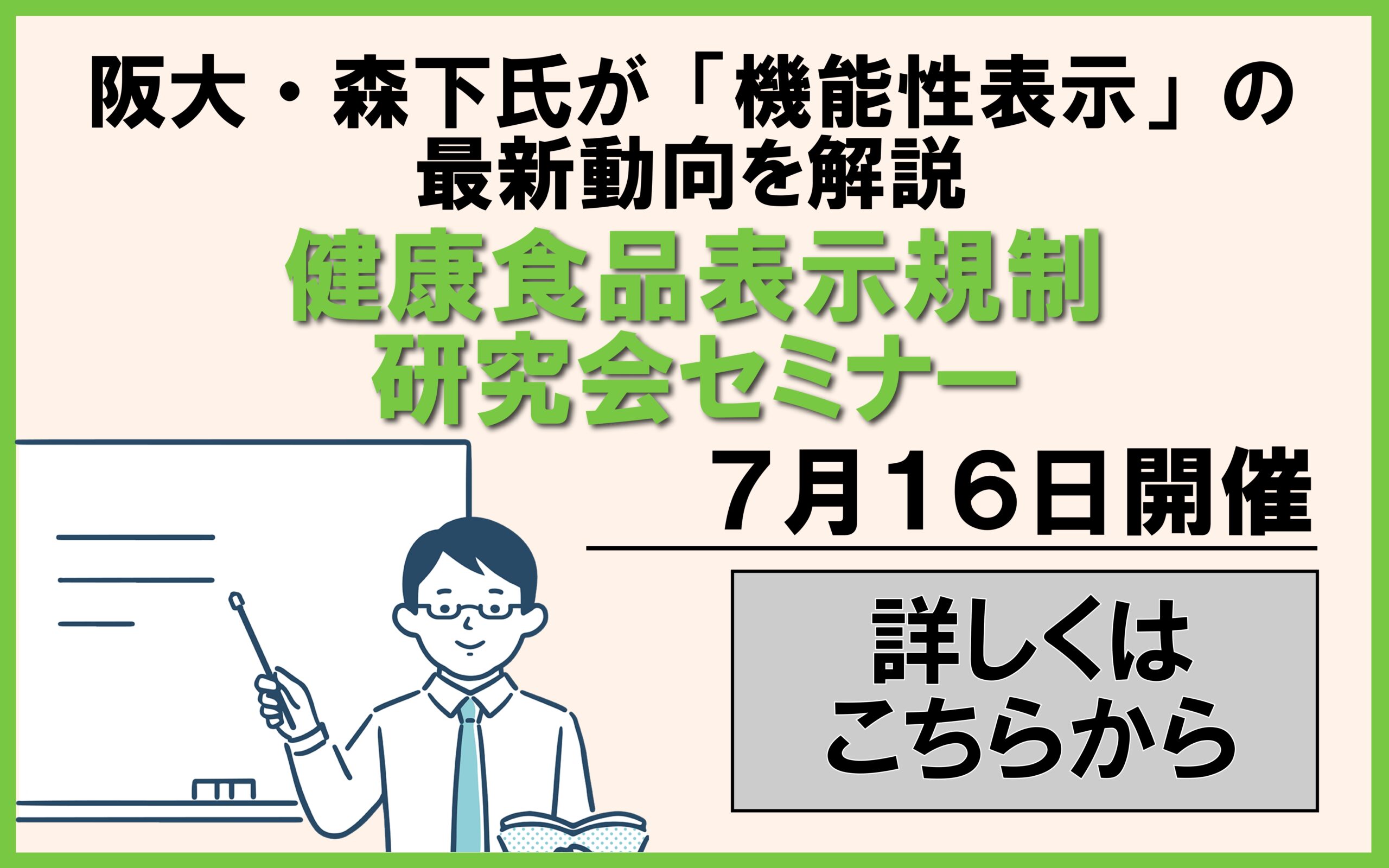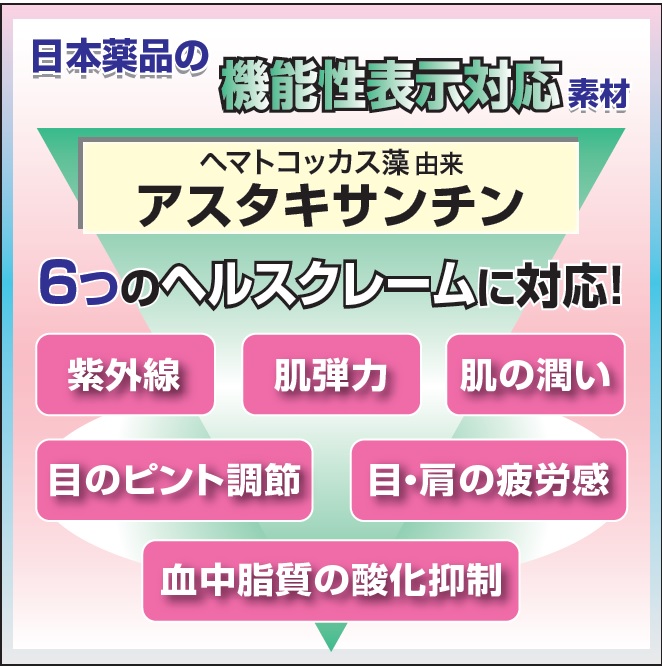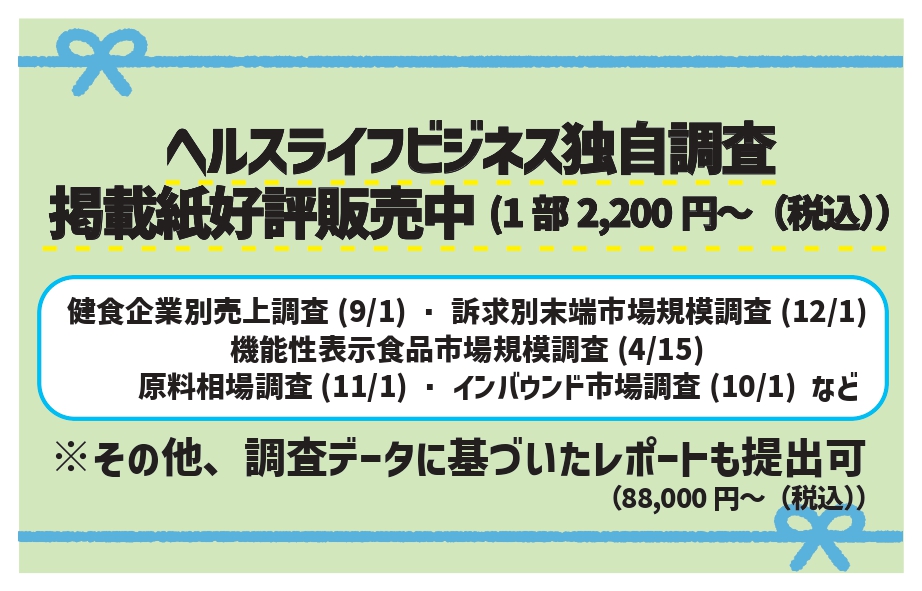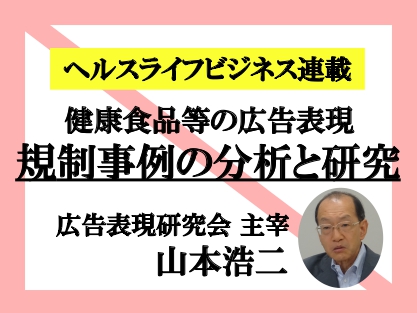業界紙の大親分に褒められる(69)
バックナンバーはこちら
出張校正室の続きである。辞書には建物など大きいものは「造る」を使うとあった。ほら見ろ、先輩のいった通りだろうと私がえばったところまで書いた。しかし続く文章を見て凍り付いた。酒や味噌を大きな工場で作る場合は「造る」を使うと書いてある。彼の当たりだった。しかし辞書の神様は私を見捨てなかった。
「おめえなんてェ者は、こんな仕事に就いて、安月給で、苦労ばっかりして、いやな部下を押し付けられて、散々だなァ~」と神様は同情したに違いない。それで辞書には続いてこうも書き込んでおいてくれたのだろう。家庭でつくる場合は「作る」を使う。この付け足しのような一行で、私は胸を撫でおろした。どうにか先輩の面子が保たれた。
それで、酒や味噌を大規模な工場でつくる場合は「造る」と言った後、「家庭や小さい工場でつくるときは『作る』を使うようだ」とちょっとだけ嘘をついた。彼にはこの小さい工場というのが効いた。
「手作りの味とか自然な製法などと書いてあるから、大規模な工場であるわけがありませんよねェ」と意外に素直だ。ということで、彼の前では「作る」に直した。しかしゲラを職人さんに戻すときにこっそりと「造る」に変えておいた。
午後になると、印刷屋の水野社長が帰ってきた。中折れ帽を被っている。といっても思い浮かぶ人は少ないだろう。ボルサリーノといえばいくらか知っている人もいるかもしれない。1930年代以降流行った帽子で、子供のころ見たシカゴのギャングのアルカポネやアンタチャブルが活躍した禁酒法時代のドラマには、必ずこれを被った男たちが登場した。私の父親も被っていた記憶があるから、結構長く流行っていたのだろう。
ところがこの社長は20世紀の後半になろうというのに、まだこの帽子を愛用している。服もダークスーツにマフラー、コートを羽織ってビッシと決めている。若かった頃はなかなかダンディだったのかもしれない。しかし今は単に変なオヤジにしか見えない。そしていつも出張校正室の引き戸をガラガラと開け、お決まりのセリフを言い放つ。
「天下の形勢はいかがですかなァ~」
とにかく声が大きい。鶏のコケコッコー!の鳴き声のようなもので、眠気に襲われていた人もシャンとするという代物だ。
「誰ですか」と寡黙な岩澤君が口を開いた。よほど興味を引かれたのだろう。ここの社長だというと、変わった人ですねという。確かに変わっている。後年この会社の50周年か何かのパーティで水野社長の一代記を聞いた。
これによると、生まれは福島県の片田舎で場所は忘れた。水飲み百姓の子供だったらしい。田舎の貧乏人はたいてい子沢山で、長男以外は都会に働きに出ないと食えない。それで高校を出ると東京に出た。しかし向学の志断ち難く、上野近くの新聞配達店に住み込みで働きながら、お茶ノ水の大学に通った。
卒業すると新聞屋のつてもあってかサンケイ新聞社の前身日本工業新聞の記者になった。しばらくすると戦後のどさくさに紛れて独立し、日本生産経済新聞社というのを起こした。
しかし戦後のインフレなどで、朝鮮戦争の特需が来る前に経営が行き詰った。このときの印刷部門を生かして新聞の印刷を始めた。これが後の成功につながった。この頃には上野の旧黒門町の工場と池之端に3つの工場を持ち、東京で有数の専門紙の印刷屋になっていた。専門紙協会の会長も務めていたから業界紙界の大親分といったところでもあった。
私たちに近づくなり、「おたくの会社は大したもんだ」と言い出した。晴海で予定している展示会のことらしい。水野社長によると、ここで印刷している新聞社は多いが、晴海で展示会をしている専門紙は他にないそうだ。
帰り際に岩澤君が「うちの会社、すごいんですね」という。実はたいしたことはないのだが、私はちょっとだけいい気分だった。
(ヘルスライフビジネス2017年2月15日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)