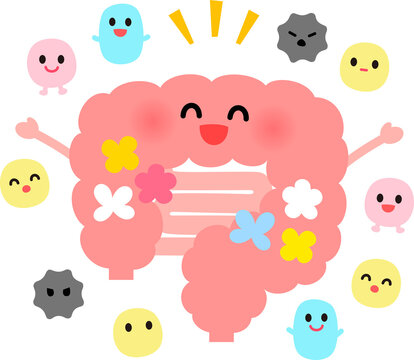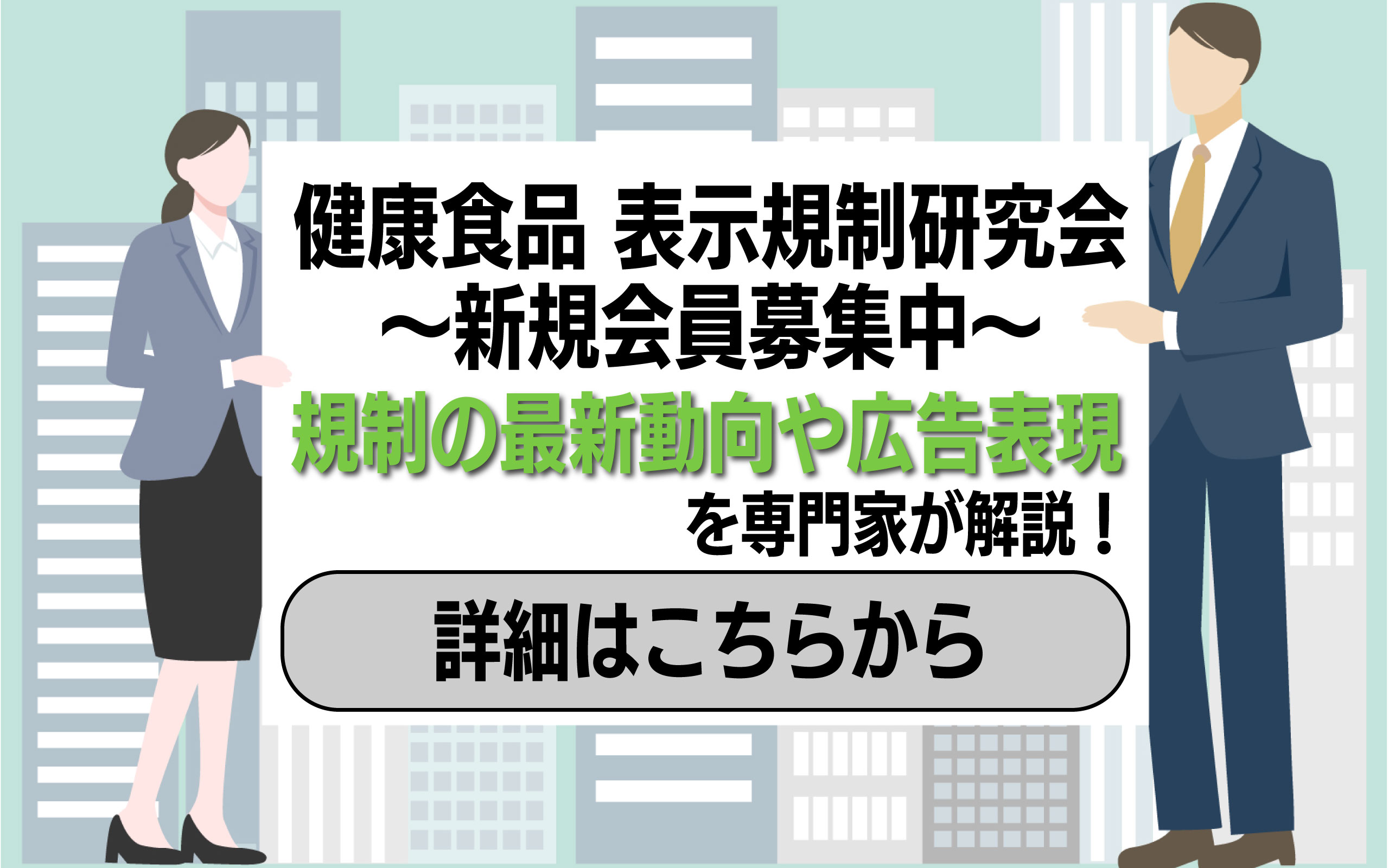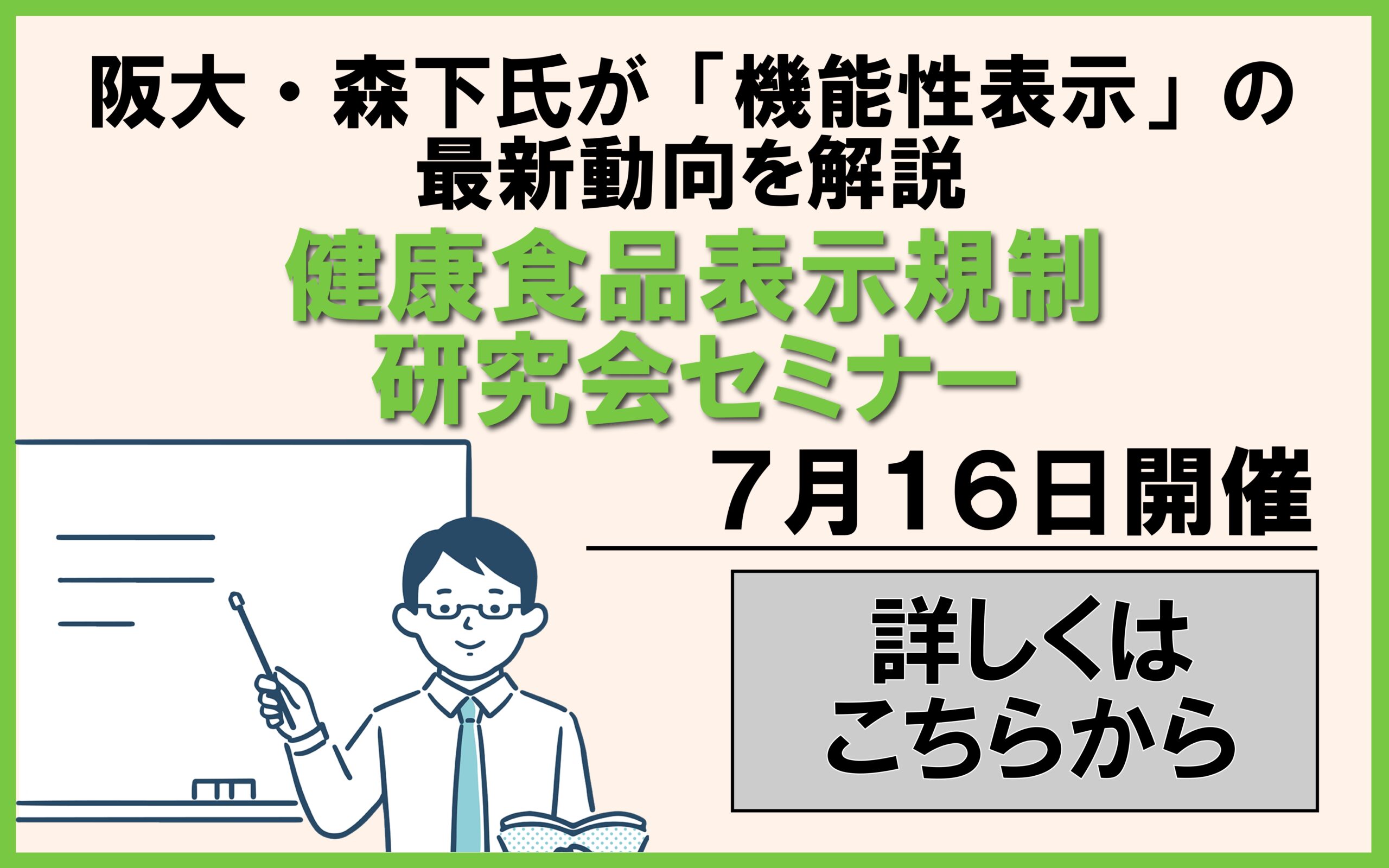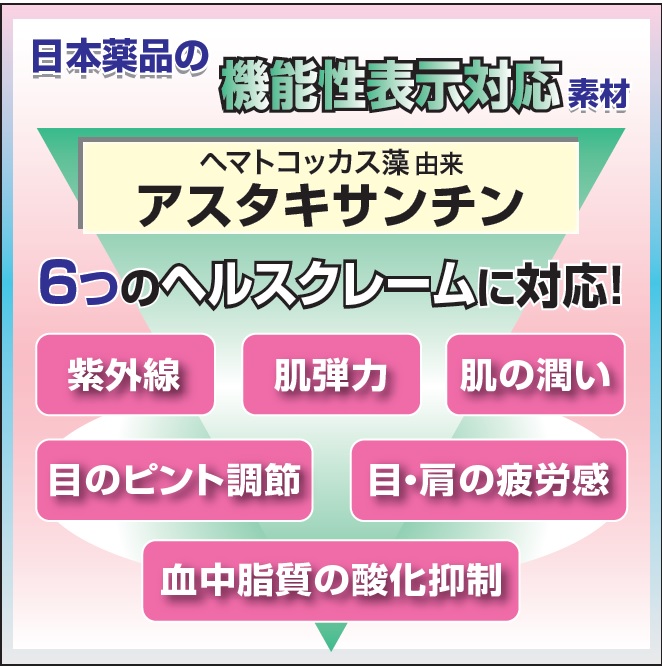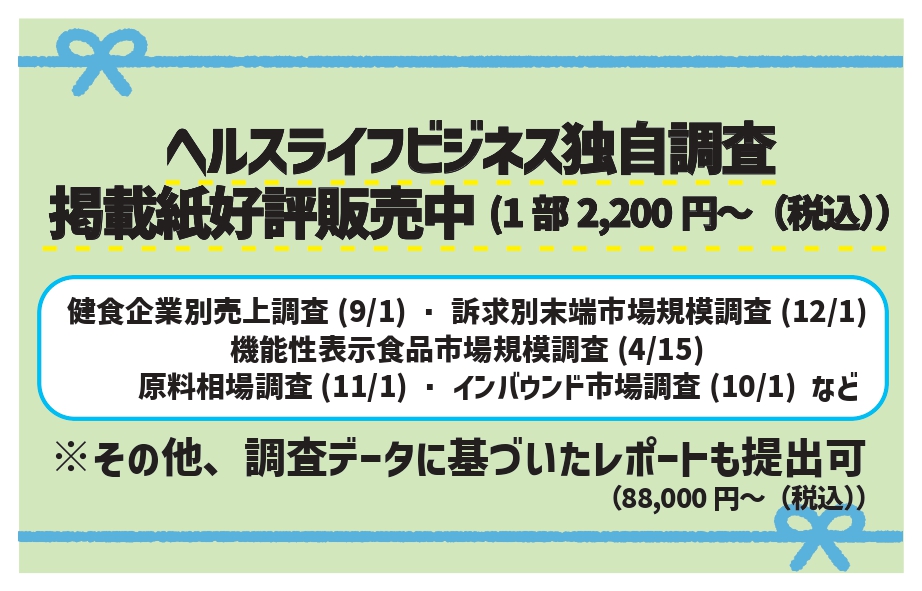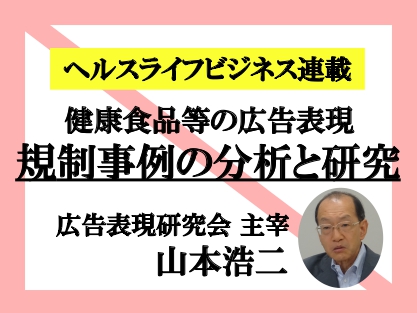“マーバラス婆”来日も、誰も英語が喋れない(71)
バックナンバーはこちら
我々の招待で展示会の前日には全米栄養食品協会(NNFA)のローズマリー・ウエスト会長が来日することになってった。NNFAは健康食品や自然食品の業界団で、1万店の小売店と製造、卸の企業が加盟していた。これは全米一の規模だったが、その頃に全米一ということは世界一ということだった。普通だったら敷居が高いのだが、会長とは前年の米国ツアーのとき会っている。それに我々は陰で“マーバラス婆”と呼んでいた。もちろん親しみを込めてだが。それで頼んだら気軽に応じてくれた。
そこまでは良かったが、考えたら誰も英語が喋れないことが分かった。英語というと「I have a pen. I have a apple.」くらいしか出来ない。さあ大変だ。俄然、英語を喋れる人を探さなきゃということになった。
今から35年前の話である。その頃英語をしゃべる人は珍しかった。もちろん、一般的には海外に行くことも稀だったし、日常的に喋る必要もない時代だった。外人さんと言うとたいがい米国人の白人のことを指したが、この外人さんと言葉を交わした記憶は中学生の時以外ない。
その頃、住んでいた東京郊外の住宅地の近くには米軍のハウスがあった。東京の周辺には、米軍基地に勤める軍人とその家族が住んでいた。ある初夏の日だった。中学校の裏庭に面した私たちの教室の窓越しに、2人の白人の娘さんの姿が現れた。授業中だった。気付いた者が「先生!誰かがいます」とその方を指さした。教室中にどよめきが広がった。それが姉妹であることは顔付ですぐに分かった。驚いたのか、その二人はすぐに立ち去った。白地に赤い花柄のワンピースに金髪の姿が印象に残った。
それを機に、時々教室を覗きに来るようになった。英語の授業中だった。雑誌「セブンティーン」からファッションを取り入れているというミニスカートがまぶしい先生だった。気付いた先生は庭に面したドアを開けて、姉妹を招き入れた。
恥ずかしそうにしていたが、先生が何かいうと、彼女たちは自己紹介を始めた。苗字はブラウン、背の幾分高い方が姉でジェシー、妹はスーザンといった。カリフォルニア生まれで、調布のアメリカンスクールに通っていた。妹の方は私たちと同じ年だったが、ずいぶん大人びて見えた。生の英語を聞いたのはこの時が初めてだった。以降英語の授業に度々来て、先生のお手伝いのようなことをした。数人の仲間と家に遊びにも行った。友人は姉からラブレターをもらったが、私には何もなかった。我々の夏休みと同時に付き合いが途絶えた。
高校生になった頃、テレビで「ビートポップス」という番組が始まった。大橋巨泉が司会で欧米のポップスを紹介する番組は同級生の間で人気になった。曲を流しながら男女が踊るのも新鮮だったが、曲の合間に踊る人の中から美人の女性を紹介するのも売り物だった。その中に数年ぶりに見る姉妹がいた。すっかり大人になり、思春期の私には刺激的だった。
それがきっかけで、再度英会話に目覚めかけた。白人のお姉ちゃんと付き合いたいというだけの邪な願望だったような気がする。当時、「百万人の英語」という英語番組がラジオでやっていた。一念発起して、本屋でテキストを買って挑戦したが、夢は2か月で潰えた。
とにかく編集部で喋れる者はいなかった。困ったが、編集長が「野尻千恵子さんは出来るかもしれない」と言い出した。彼女はこの新聞社の先輩で、葛西博士や私がこの会社に入る前に記者をしていた。ところが私が入った頃には辞めていて、家具の会社の社長秘書をやっていた。
それでも暇があると、時々編集部に遊びに来るので知っていた。私より年上で、仕事でも先輩だから辞めても、来ると大きな顔をしていた。結構、いい給料をとっているらしく、そのことは服装からも分かった。その野尻さんがなぜ英語を喋れるのかは忘れたが、とにかく片言だったらできるということで引き受けてもらった。
(ヘルスライフビジネス2017年3月15日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)