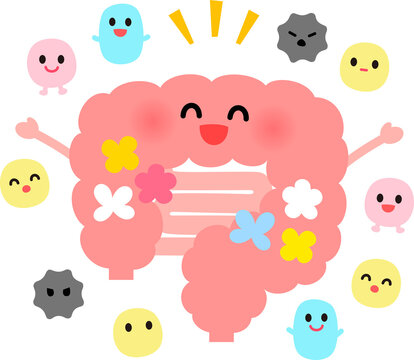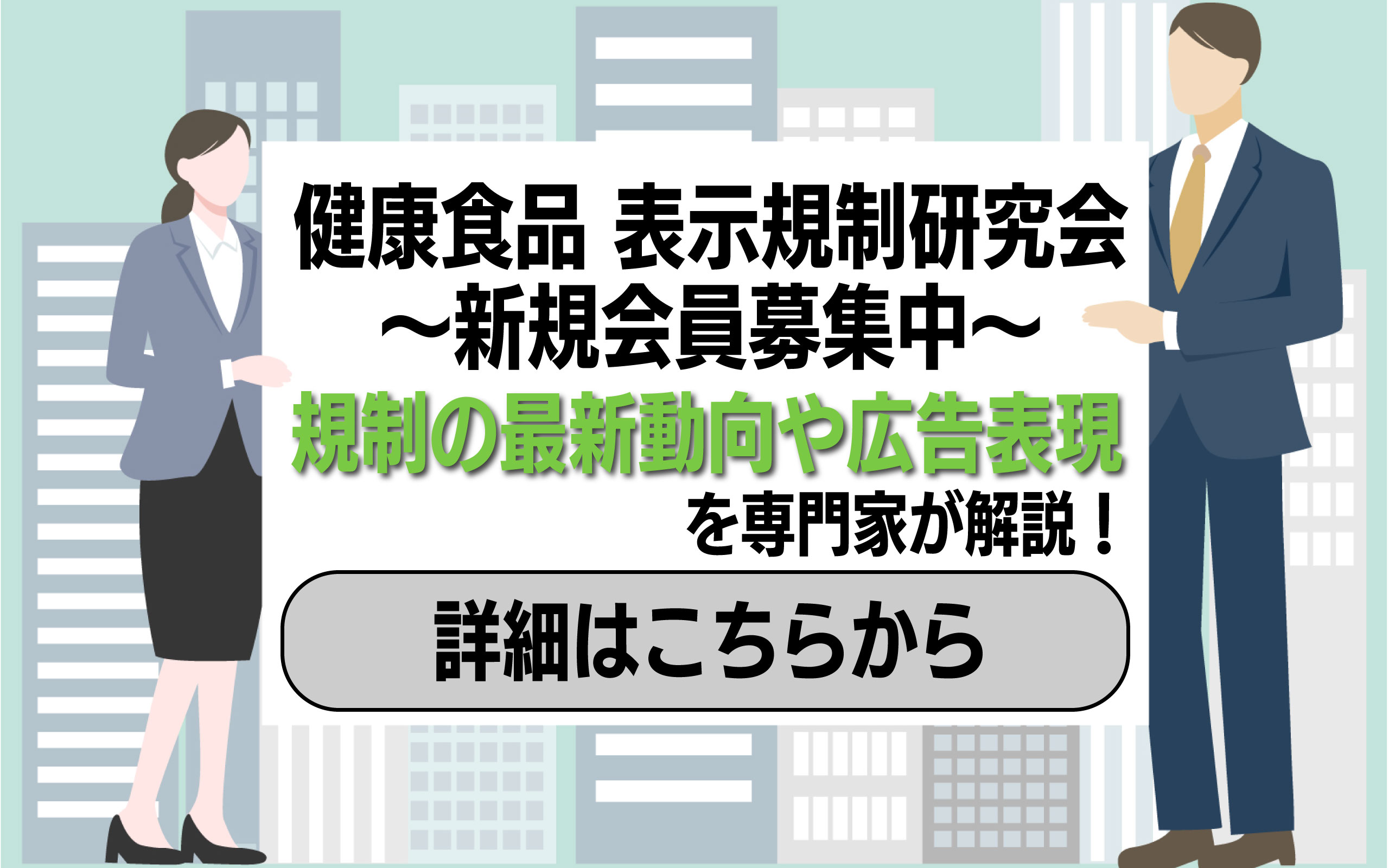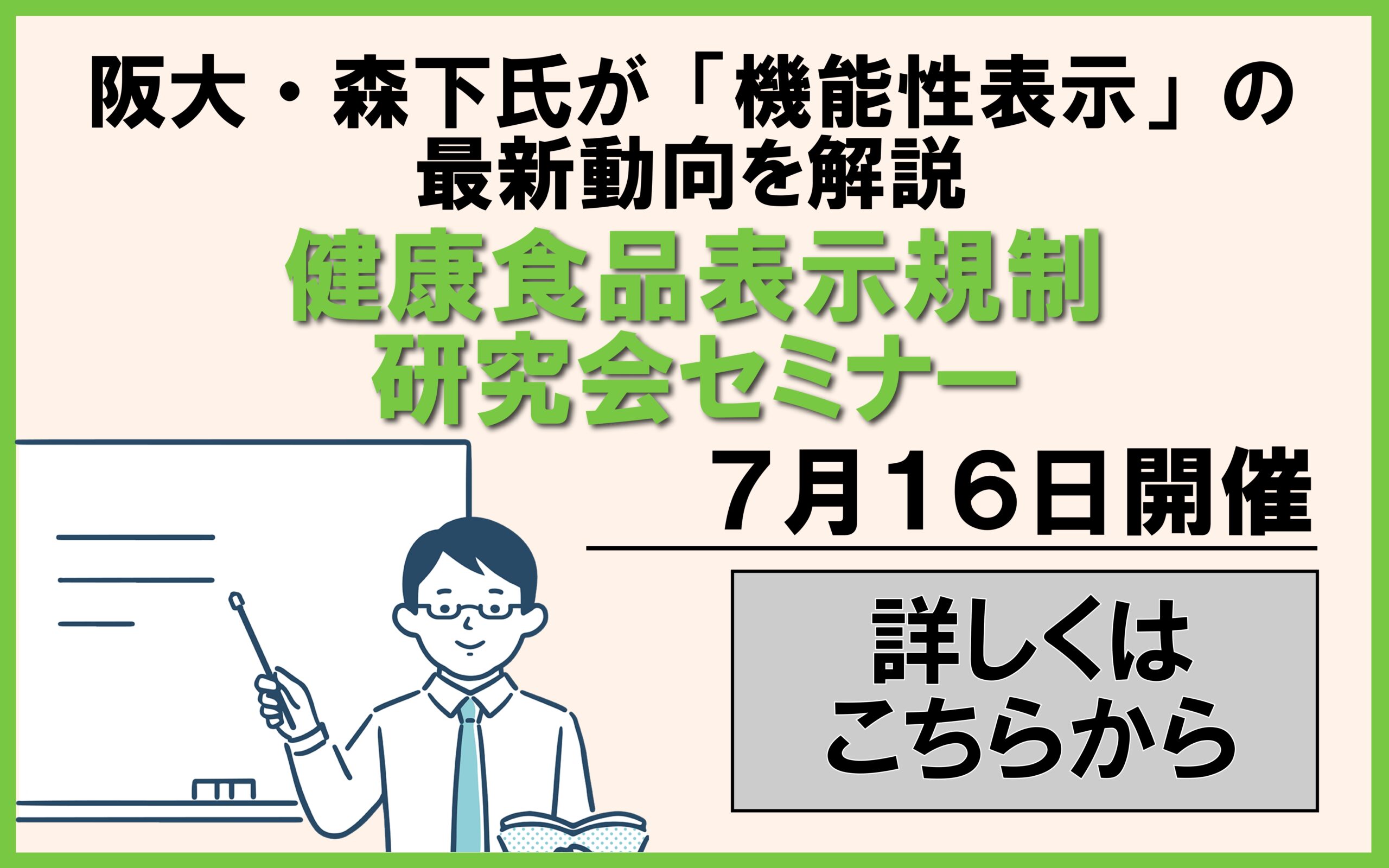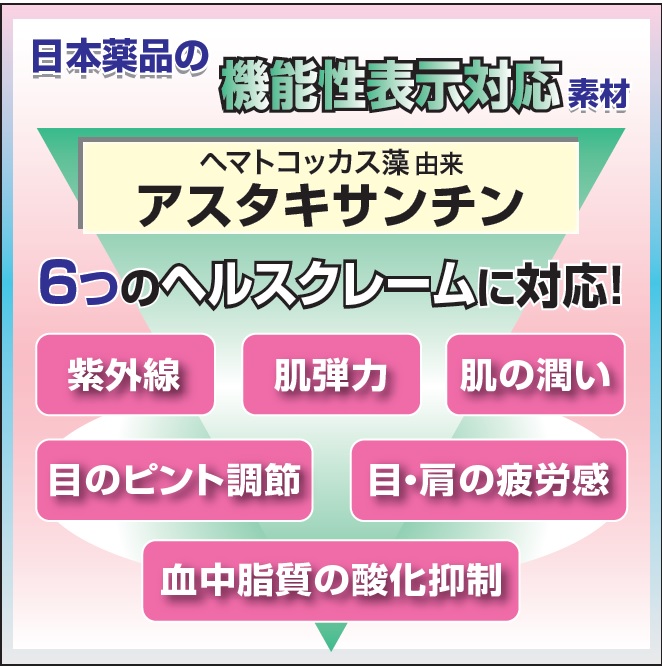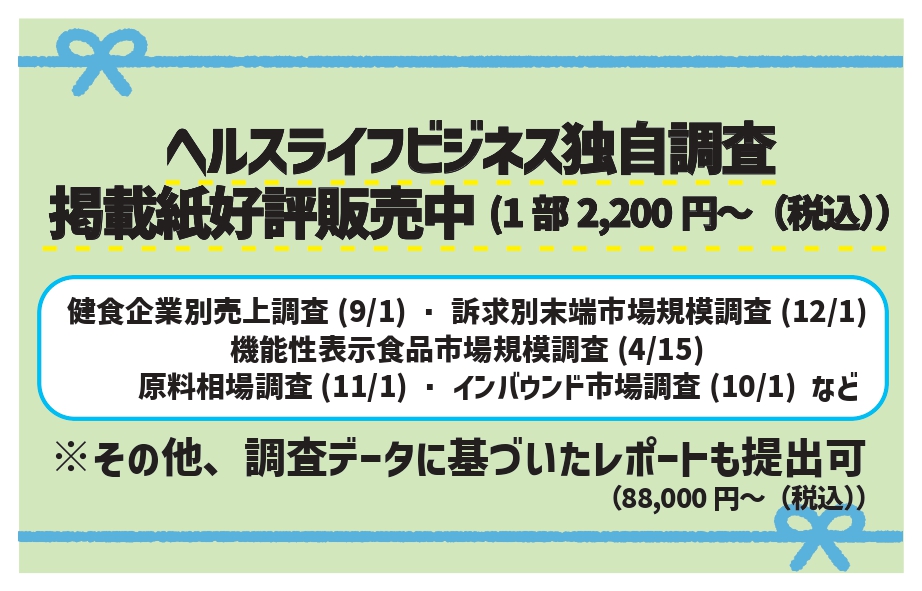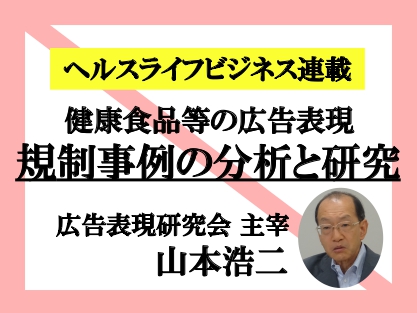サプリ屋になった青山さんの数奇な人生(102)
バックナンバーはこちら
1年数か月前のことを思い出した。その日、編集部を茶色のジャケットを着た中年の男性が訪ねてきた。名刺には日本オルト食品の青山勝彦と書いてあった。
数日前に編集長から話があった。
「渡辺先生の紹介で青山さんという人が来るからよろしく頼む」という。自分は用事が出来て、関西に行かなくてはならないので、代わりに会えということらしい。要件はなんでも健康食品の仕事を始めるので力になれという。
そして「先生はお兄さんの紹介だといっていた」と付け加えた。渡辺先生のお兄さんと言えば以前にも書いたが、その頃朝日新聞の社長をしていた渡辺正毅さんだ。健康食品をやろうという人が、なぜ天下の朝日新聞の社長と知り合いなのか。
「なんだかねェ。とにかく粗略にはできないということだ」と葛西博士。
後年知ったことだが、青山さんは数奇な人生を辿ることになる。生まれは何処だか知らない。しかし学校は早稲田大学の政経学部を出たようだ。勉強ができたわけだが、どうも大学で芝居に凝った。これは健康食品に辿りつくために辿らない道だった。
早稲田大学は古くはシェクスピアの坪内逍遥、新劇の島村抱月、我々の時代には鈴木忠志の早稲田小劇場、天井桟敷の寺山修司など逸材を輩出した大学である。いわば芝居のメッカでもあった。
その中に入った青山さんは弁護士にも、政治家にも、商売人にもならずに、芝居の演出家になった。ところが社会に出てみると、これではなかなか食べて行けない。それで週刊誌のライターになった。唐突なようだが、おそらく文才があったのだろう。そしてさまざまな記事を書くうちに、朝日新聞で起きていた問題を取り上げた。これが縁で出版の責任者だった渡辺正毅さんと知り合った。
そのとき取材した記事を大変ほめてくれたそうだが、その記事で青山さんは賞も取った。ジャーナリストとしての全盛期だろう。
しかしそんなジャーナリストが、なぜ健康食品の世界に入ることになったのかというと、それなりの事情がある。週刊誌の記者は大半がフリーだ。原稿で食べて行かなければならない。
ところが不況になればしわ寄せは弱い立場の者に来る。戦後、高度成長を続けてきた日本経済は1974年の石油ショックで終わりを告げて、不況の時代を迎える。景気が冷え込むと消費は鈍り、企業はまず出費を減らす。
なかでも広告宣伝費は予算を抑える最初の対象になる。広告の出稿が減れば週刊誌の売り上げも減る。さらに不景気でお父さんの給料が上がらなければ、お母さんたちはたちどころに財布のひもを締めて来る。お小遣いが減れば、通勤途中の駅の売店で新聞や週刊誌を買うのも控えがちになる。こうなると、売り上げ部数にも影響が出る。こうして不況のしわ寄せはフリーのライターに押し寄せる。
仕事が減ったころ、青山さんのところに地方自治体からの高齢者に関係した企画書の依頼が舞い込むことになった。65歳以上の高齢者の割合が人口の7%を超えると高齢化社会という。1970年に高齢化率は7.1%を超えて、日本はすでに“高齢化社会“になっていた。このため73年から無料化されていた老人医療費が高齢者の増加で国の財政を圧迫して、前年に老人保健法が成立した。
この頃、カルシウムをまぶしたお米の事業と出会う。これが健康食品の事業に発展することになる。青山さんが訪ねて来た時に、何を話したか覚えていない。おそらく大した話はしなかったのだろう。
ただし、その時の姿は目をつぶると今も鮮明に覚えている。とにかく青山さんは我々と同じ渡辺正雄先生の弟子となった。
しかし、我々と違うのは毎月送ってくれる「渡辺レポート」をまじめに読んだことだ。
なかでも欧米の先端の栄養学を学ぶ中でビタミンB群に興味を持ち、日本で食品として初めてのビタミンB群のサプリメント「ビオスバイタミンB」を出した。それが西武のバイタミンコーナーに並んだ。このコーナーがテレビや雑誌で紹介されるごとに、「ビタミンバイブル」と,このビタミン群のサプリメントが画面に写し出される。
これが青山さんのビジネス成功のきかっけになった。
(ヘルスライフビジネス2018年7月1日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)