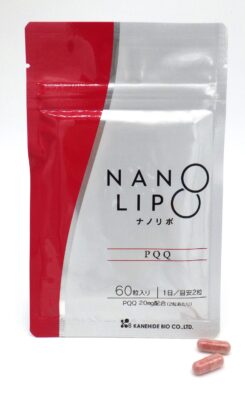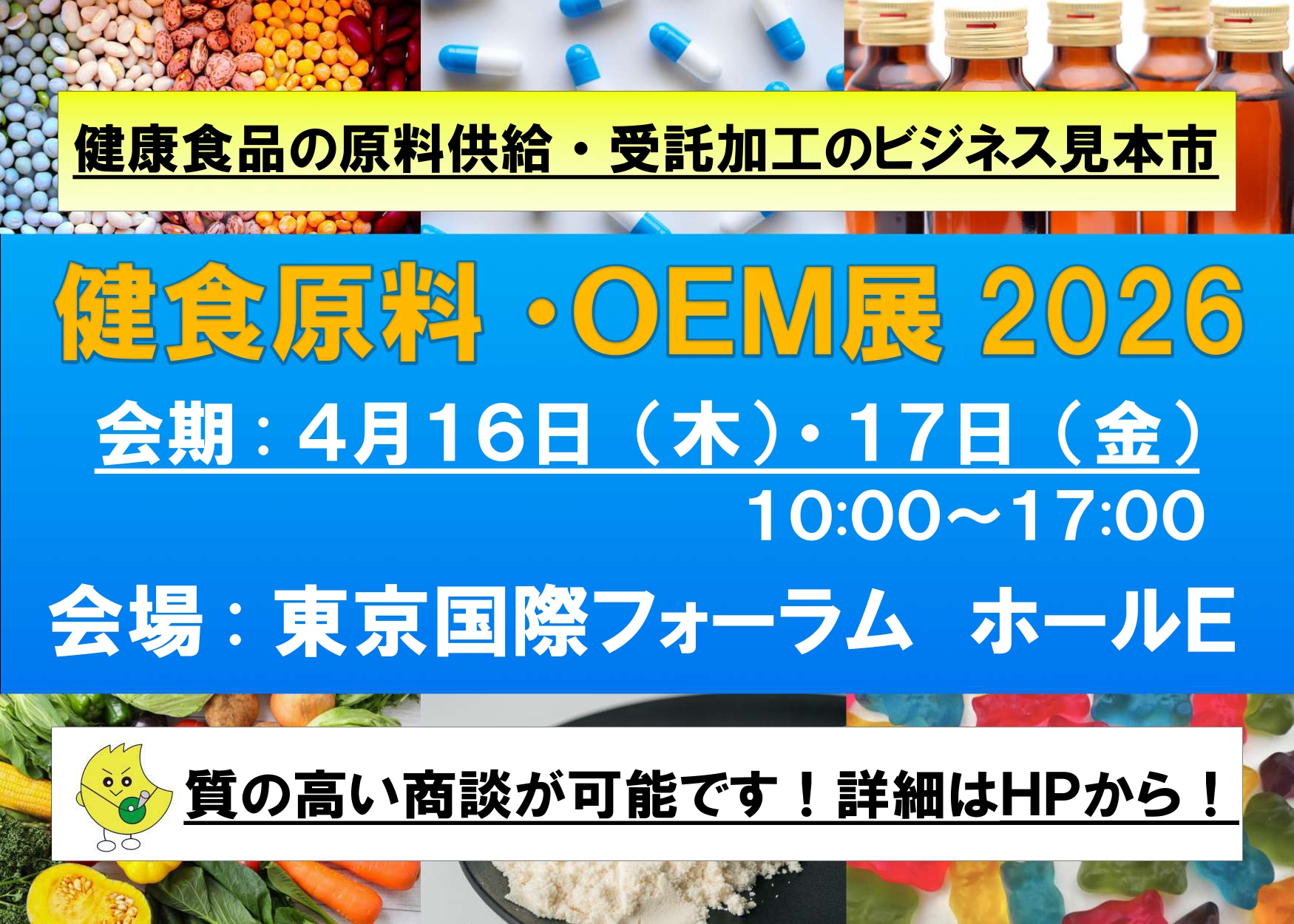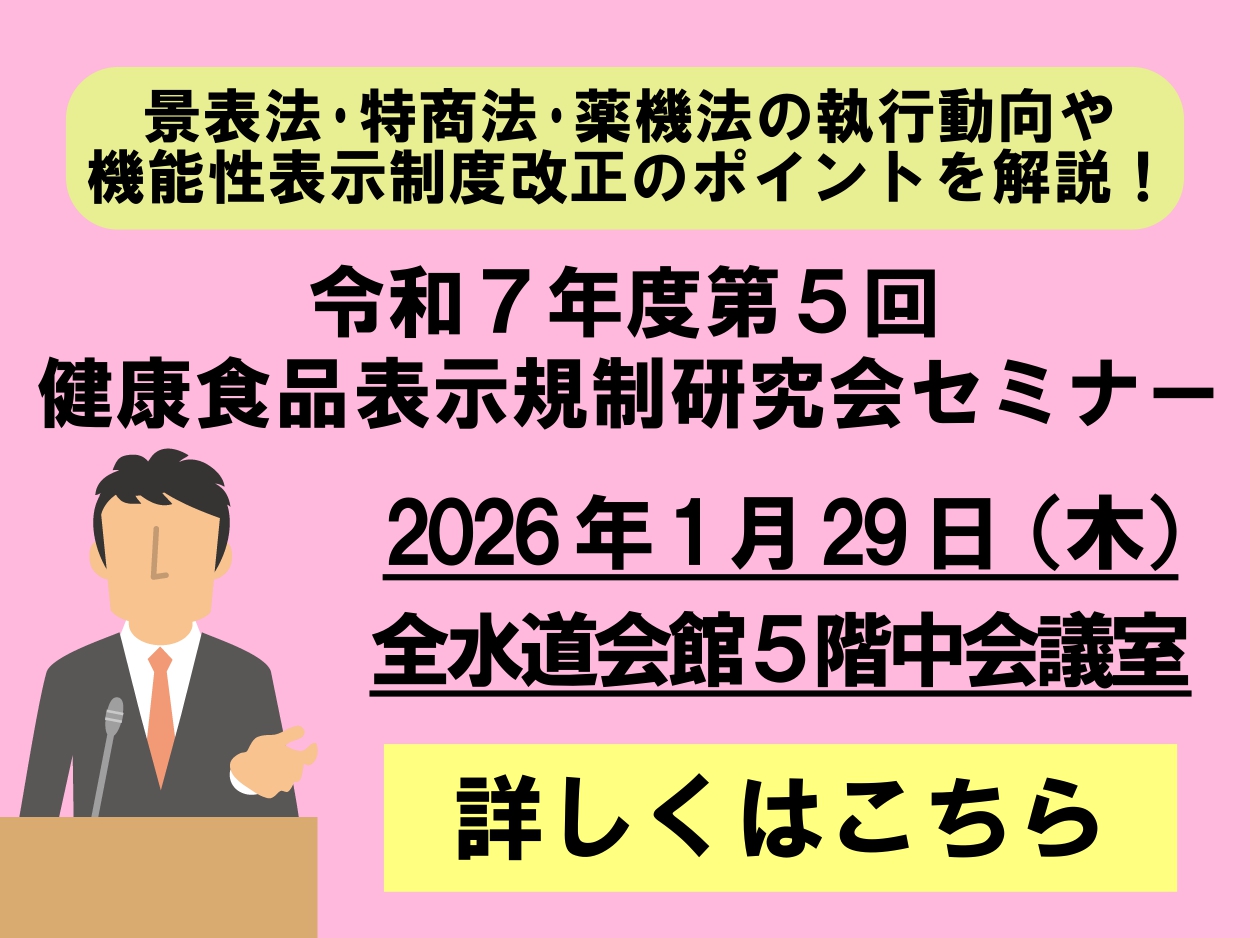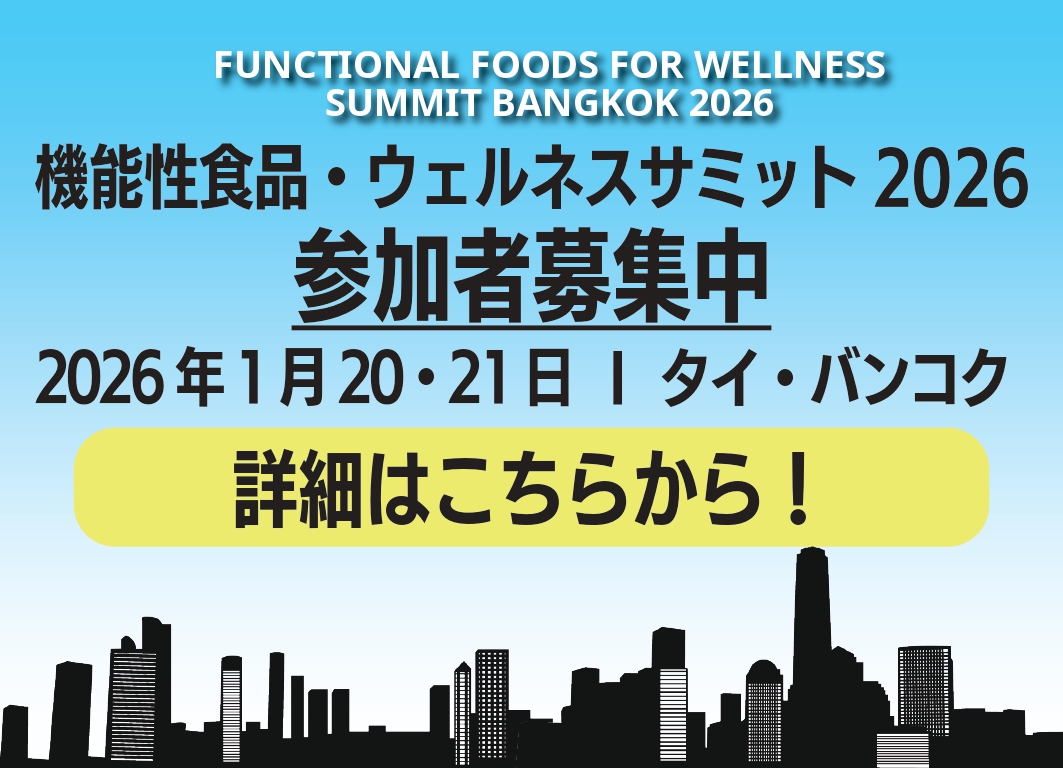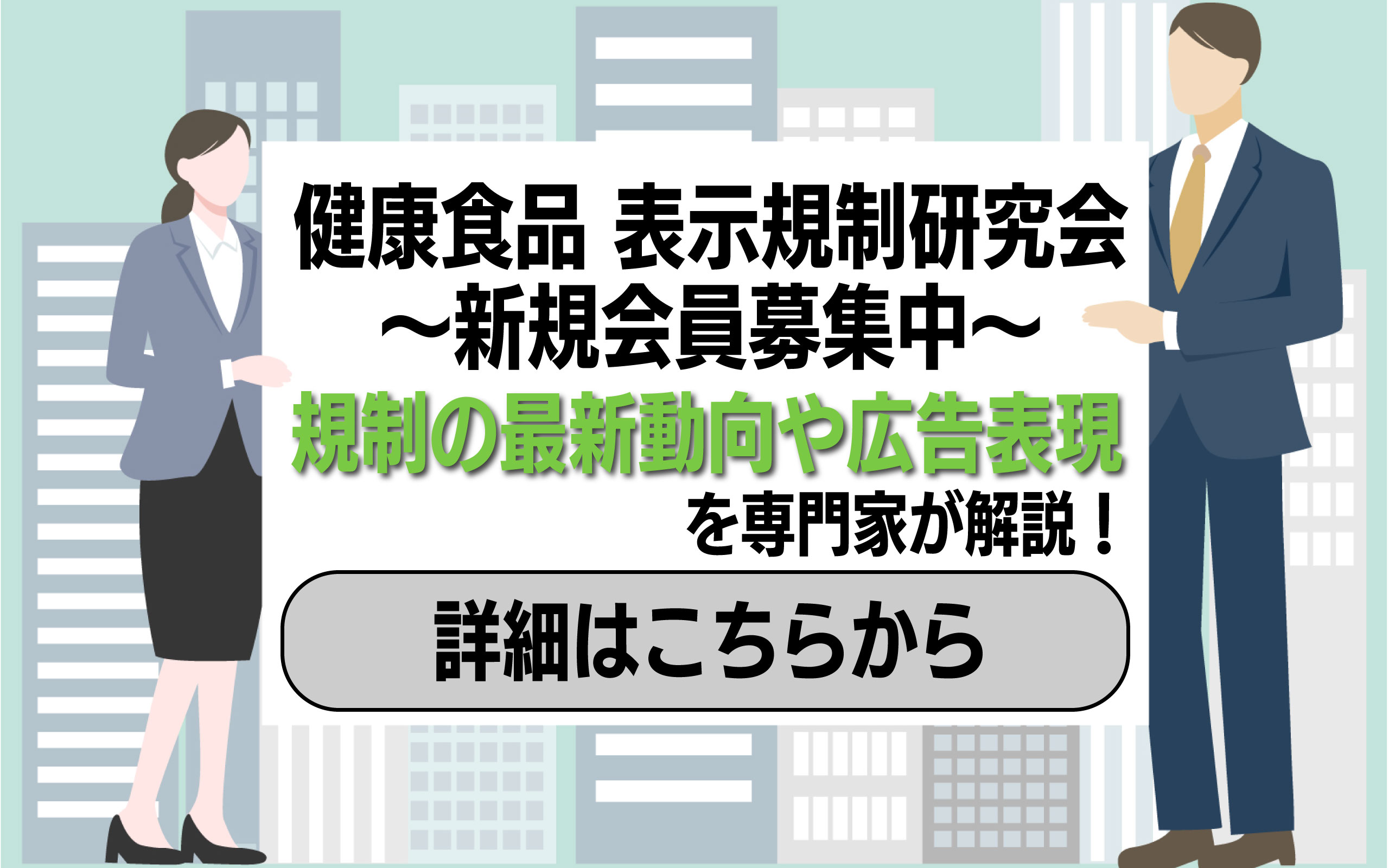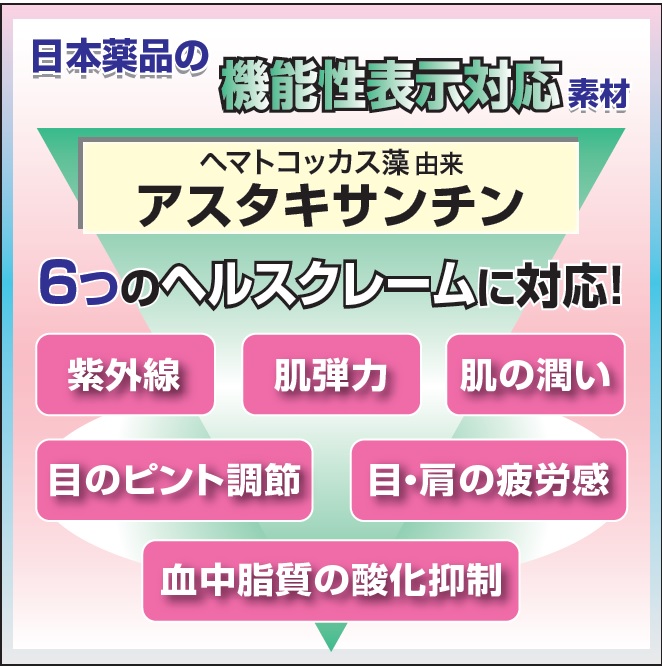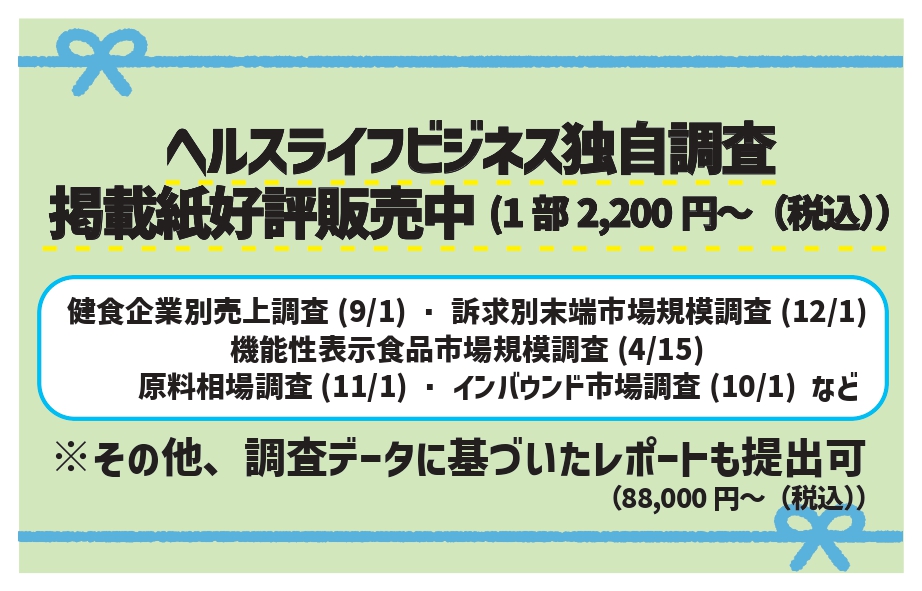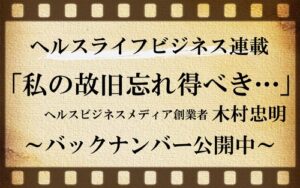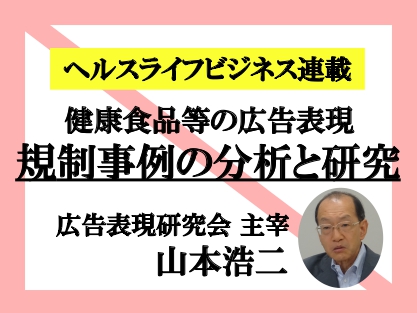- トップ
- ビジネス , ヘルスライフビジネス
- “古い栄養学”から“新しい栄養学…
“古い栄養学”から“新しい栄養学”へ(148)
バックナンバーはこちら
出版記念の講演会には結構人数が集まった。すでに渡辺正雄という名前は業界に知られていた。最初は我々の新聞でも何度も新しい栄養学の連載をしてもらっていたし、講演もしてもらっていた。そのうち業界団体の講演にも呼ばれるようになり、この頃にはそれなりに渡辺ファンが出来ていた。
当日は100名を超える聴衆が集まって、会場は満杯になった。最初にお茶の水女子大の福場博保教授が登場した。福場さんは国の栄養政策を作っている方で、どちらかと言うと渡辺先生の言う“新しい栄養学”の方ではなく、“古い栄養学”の方の人だった。
“古い栄養学”を基盤にした国の栄養政策にはいくつかの柱がある。健康に暮らすために必要な栄養の量を定めた「日本人の栄養所要量(日本人の食事摂取基準)」である。これとセットなのが、献立を作るときに使う食品の栄養価を定めた「日本食品標準成分表」である。現在では2191品目の食品(2015年)だが、当時は1621品目の栄養価を定めていた。そして所要量が定めている栄養の量が摂れているかどうかを年1回調べる「国民栄養量調査(国民健康・栄養調査)」がある。この結果は通信簿のようなもので、毎年必要な栄養が摂れているかどうかを調べて発表する。
「日本人の栄養所要量」は1970年(昭和45年)から始まり、5年ごとに改定されている。また「日本食品標準分析表」を最初に作ったのは日本の栄養学の父と言われる佐伯矩(さえきただす)だと言われるが、国が作るようになったのは1950年(昭和25年)からで、これは1947年(昭和22年)栄養士の制度が始まったためとみられる。
さらに「国民栄養調査」の初めは昭和20年だが、今とはだいぶ意味が違う。戦後の食糧難で米軍から援助を受けるため、連合軍最高司令部(GHQ)の指示で行われたらしい。今のようになったのは1952年(昭和27年)に栄養改善法が出来てからで、これからようやく国民の健康や栄養状態を把握するために行われるようになった。
とにかく栄養政策は第2次世界大戦が終わってから今のように行われるようになった。これは戦後民主主義の象徴のようでもある。天皇のための国家から国民のための国家になったのだ。国は国民の健全な栄養状態を維持して、健康に奉仕しなければならなくなったのだ。
それを象徴するようなものに、もう一つの栄養政策として「食生活指針」がある。最初にこれが出されたのは、なんと終戦の日の1945年の8月15日だ。戦争は終わったが、日本は未曽有の食糧危機にあった。今ではこれは国民の健康のための栄養の改善のガイドラインだが、その頃は飢えを耐え忍ぶためのガイドラインだったのだ。面白いことに主食に玄米や雑穀、さらに野草などの食用にすることを推奨している。
しかしこれ以降これは1985年まで出されていない。飢えは遠の昔のことになり、好きなものをいつでも食べられる豊かな社会になったので、もう必要ないと考えたのだろう。ところが世は飽食の時代を迎えていた。そして戦後理想の食事としてきた欧米の食事に突如赤信号が灯ったのだ。
1977年に米国上院はマクガバンレポートを出して、理想的な食事だったはずの欧米の食事が現代病を作り出していると指摘された。豊かさを謳歌していた米国社会に激震が走った。さらにその改善の目標として、ダイエタリーゴール(食事目標)が出ると、社会を挙げて食事改善運動が始まった。
日本の栄養学者たちは慌てた。マクガバンレポートでは日本食が健康に良いというのだ。戦後推進してきたことと真逆の方向に世界が動き出したのだ。素知らぬ顔をして方向転換した。農林水産省が「日本型食生活の勧め」という農水省版の「食生活指針」をまとめた。福場さんはその委員でもあり、この大転換期にある栄養政策の渦中の人だった。厚生省はこの翌年に「健康づくりのための食生活指針」をまとめる。
講演に立った福場さんは戦後の貧しい時代を抜け出し欧米に近づいてきたが、その一方で様々な健康問題を引き起こしているとして次のように指摘した。
「日本人の食事は国民栄養調査でも明らかなように、平均としてはバランスが取れていますが、全体としてはバラつきの多い食生活を送っている」
つまりこの栄養の過剰やアンバランスががん、心臓病、脳血管疾患などの西洋型の現代病を生んでいるというわけだ。ここで福場さんは渡辺先生の”新しい栄養学”の考えにつながって行く。
(ヘルスライフビジネス2020年6月1日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)