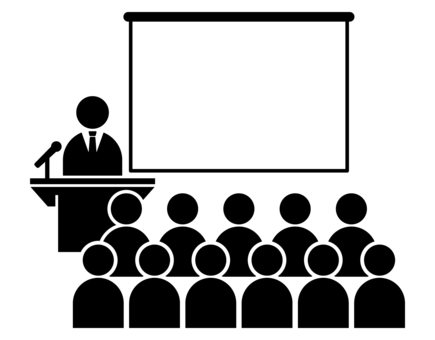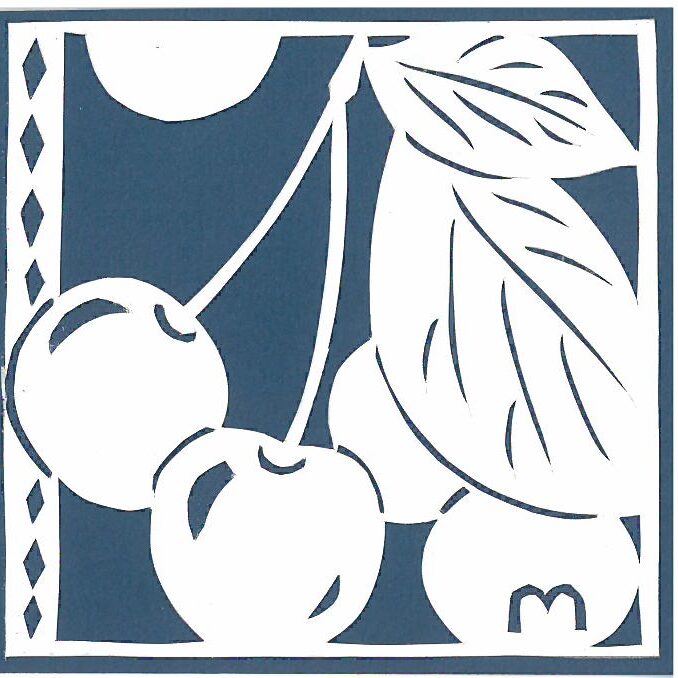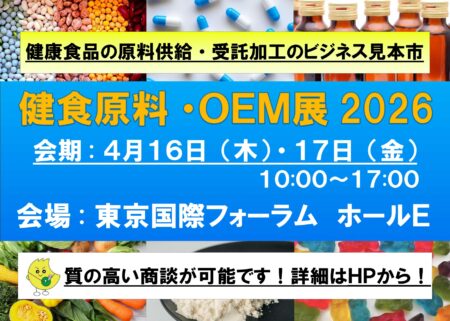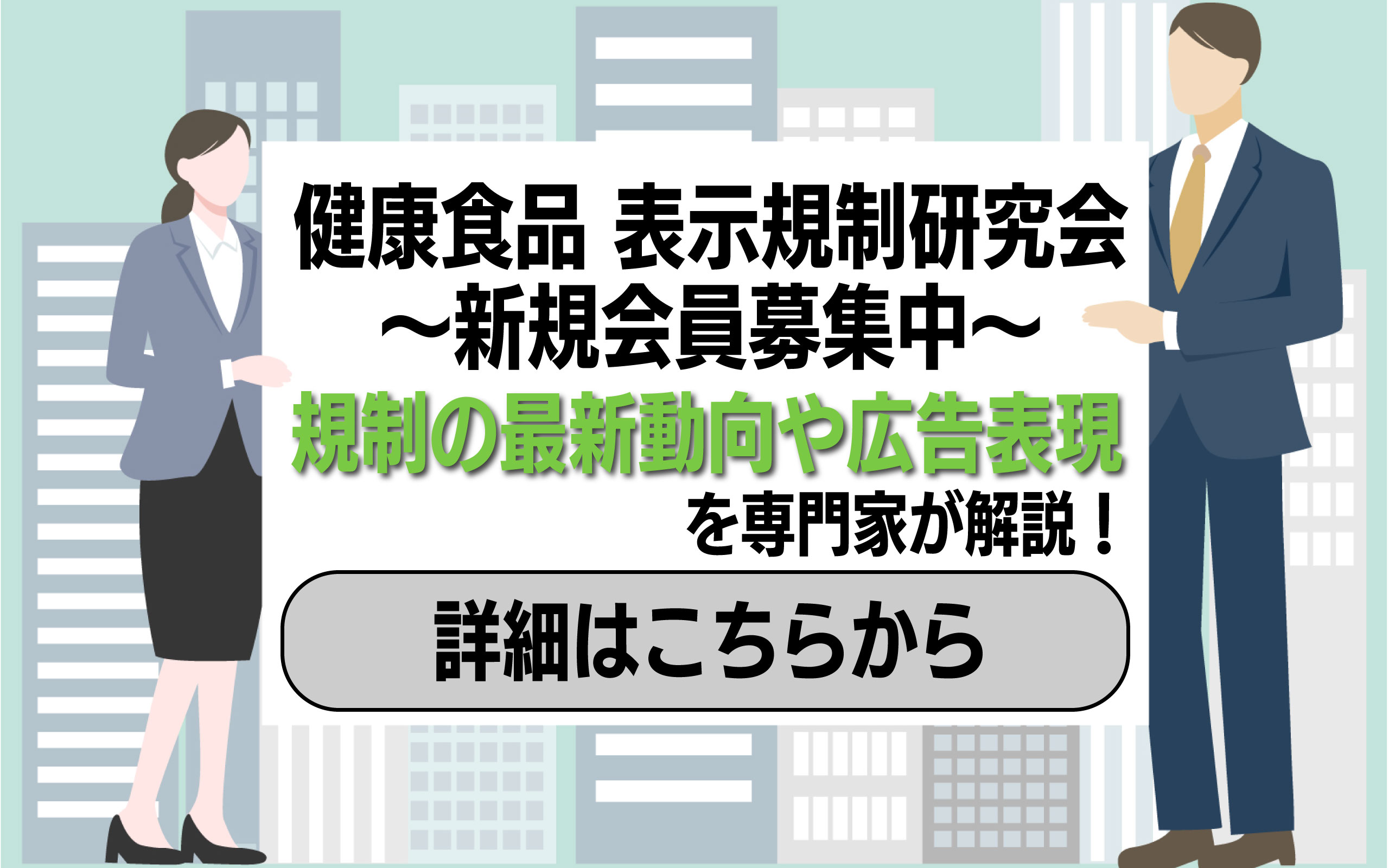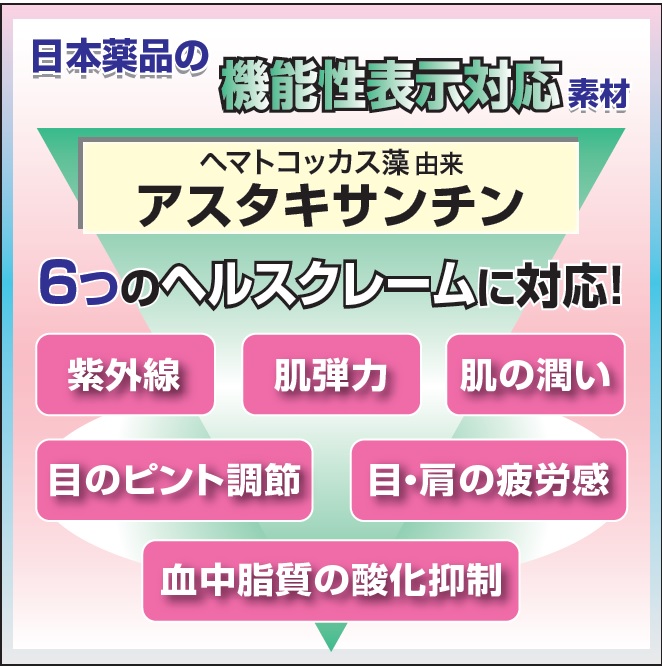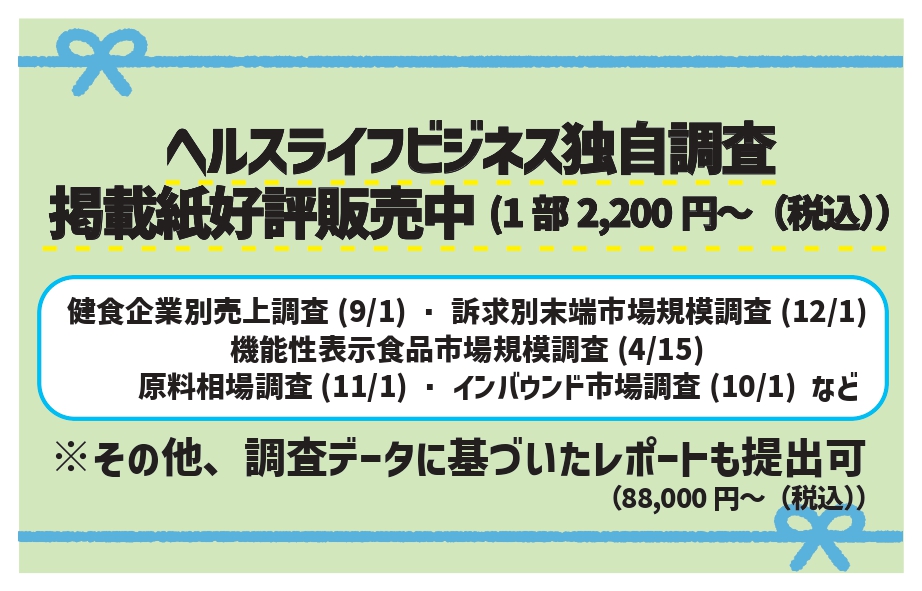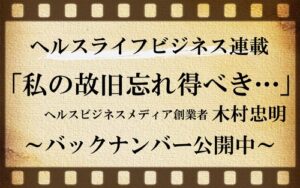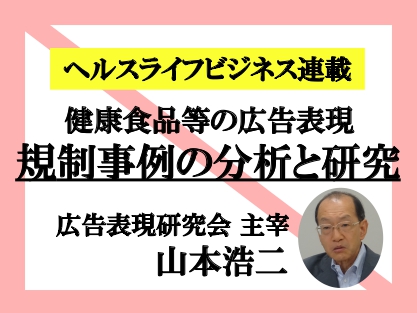- トップ
- ニュース , ヘルスライフビジネス , 健康・美容製品
- 【インタビュー】広島大学病院 …
【インタビュー】広島大学病院 未来医療センター 東川氏
【インタビュー】
「質の高い論文が機能性表示食品の立ち位置向上に」
広島大学病院 未来医療センター 食品臨床研究部門 東川史子氏
‐先生のお取り組みについて教えて下さい。
東川 食品臨床研究の実施、ならびに特定保健用食品申請や機能性表示食品届出支援をしています。システマティックレビューについてのご相談も受け付けております。
当センターを立ち上げたのは3年ほど前ですが、私は前の研究室から臨床研究を行ってきたためトータル19年ほど携わっています。これまでに血糖、血圧、血中脂質、BMI、肝機能、酸化ストレス、疲労感、睡眠などの評価項目で42件の臨床研究実績があります。
‐貴センターの特徴は。
東川 まず、継続的に臨床研究を行うことのできるシステムを確立しています。母集団での効果を正しく評価するためには、なるべく幅広い集団から被験者を集めなければなりませんが、当センターでは一般市民の研究参加希望の登録者をデータベース化しています。やる気に溢れた被験者さん5500人以上が登録しています。
また、長年積み重ねてきたノウハウが被験者脱落率の低さやクオリティの高い研究に繋がっていると思います。
臨床研究は成分をきちんと摂取していただきしっかり記録をつけなければデータになりません。被験者ありきといいますか、学術的な部分だけが大切なのではなく被験者との信頼関係が大事です。関係を築いているとコンプライアンスが非常に良いです。試験後、名残惜しいと言う方もいるくらいです(笑)。
費用面もリーズナブルだと思います。大学ですから利益が必要なく、「良い成分を世に出したい」という気持ちでやっています。国立大学ということで世間からの信頼度が高いという点を常に意識し、透明性と公正性を重んじて、独立した視点から信頼に足る臨床研究結果を報告しています。
特にできない分野はありませんが、得意分野は腸内マイクロバイオーム関連です。
‐食品機能の臨床を希望する企業からの問い合わせで目立つ素材や分野はありますか。
東川 素材はさまざまですが、睡眠に関する依頼が立て続けにあり驚きました。実際、睡眠でお困りの人は多いです。試験の投げかけをすると応募が殺到しました。治療中の方は対象外ですが、応募できなかった服薬している方もたくさんいますからね。少し前は免疫関連の相談も多かったです。
‐19年に施行された臨床研究法や昨年の紅麹事件で影響はありましたか。
東川 臨床研究法が出来た時は大荒れでした。「食品の臨床研究が研究法の対象になるのかどうか」を誰も答えられず混乱状態でしたが、現在はフローチャートで綺麗に区分され問題無いです。
紅麹に関しては、悲しい事故ではあるけれども紅麹自体が悪いわけではなく、機能性表示食品がどうこうという問題でもないじゃないですか。きちんとした成分が批判されることはいけませんし、「機能性表示食品は危ない」と根付いてしまったら残念だと思っていました。
‐食品機能の臨床研究について今後の課題とは
東川 一研究者として、根拠が曖昧な成分について、なんとかしなければならないのではと思っています。
普段から機能性表示に届出受理されている成分について根拠論文を読む機会が多いですが、正直、お粗末な論文も実際あります。
全体のクオリティを上げていくことで、消費者も安心して使えるようになりますし、機能性表示食品の立ち位置が上がることに繋がると思います。
論文の質が低いという点に消費者庁や業界団体がメスを入れ始めているとは思うので、今後厳しくなっていくでしょう。
‐ありがとうございました。

↓↓↓ 購読(電子版・紙版)のお申込みは以下よりお願いします ↓↓↓